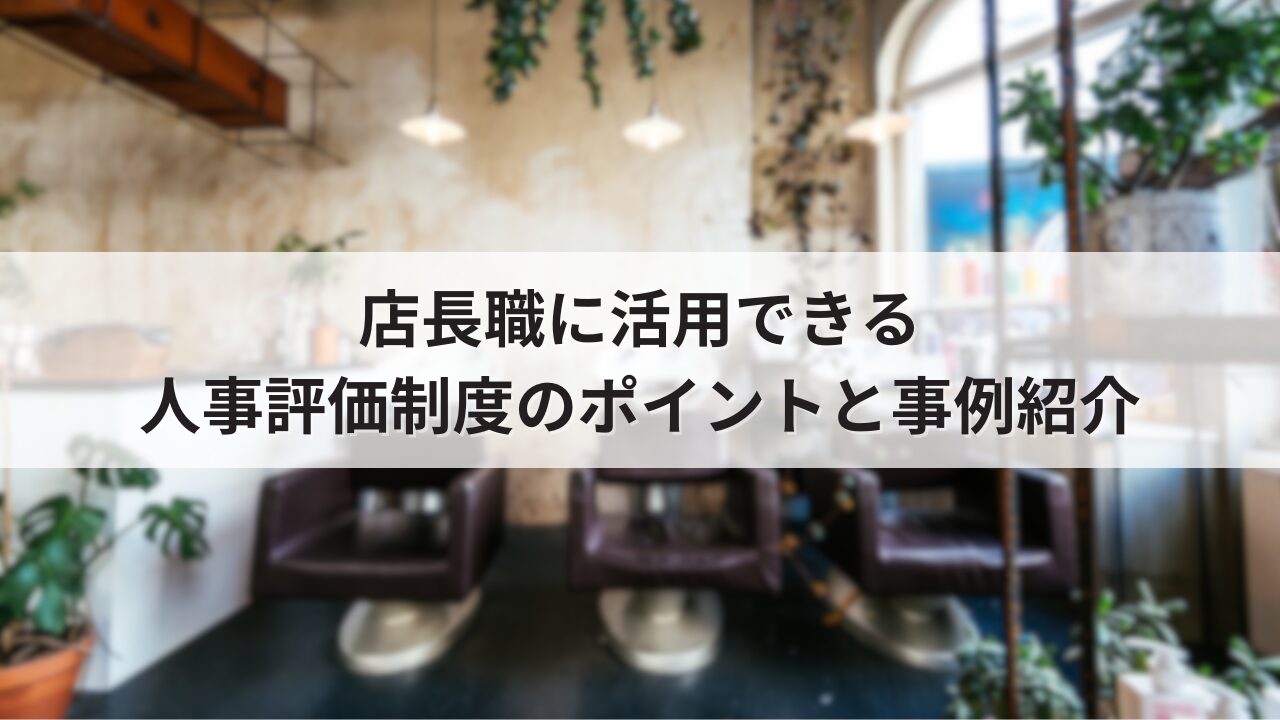- 美容院に特化【第1回】| 成功する評価基準と運用ポイント
- 美容院に特化【第2回】| 人事評価制度を導入するメリット、デメリット
- 美容院に特化【第3回】| アシスタント職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第4回】| スタイリスト職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第5回】| 店長職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第6回】| エリアマネージャー職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第7回】| 専門職(アイリスト、ネイリスト)に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第8回】| 効果的な人事評価制度の導入と成功の秘訣
1. はじめに
本コラムの目的と背景
これまでの連載では、中小美容業における人事評価制度の重要性や、アシスタント職・スタイリスト職など各ポジションごとの評価項目や運用のヒントを解説してきました。いずれの職種でも、人事評価制度の導入が「採用力の強化」や「離職率の低減」「スタッフのモチベーション向上」「業績アップ」につながる可能性が大いにあることが分かってきたかと思います。
しかし、美容サロンにおいて店舗運営の最前線でマネジメントを担うのは店長職です。店長は、売上管理やスタッフの育成・配置、顧客満足度向上のための施策など、実に多岐にわたる業務をこなさなければなりません。ゆえに、店長の能力や行動がサロン全体の雰囲気や業績を大きく左右します。
今回のコラムでは、店長職の人事評価がなぜ難しいのかをまず整理し、そのうえで適切な評価項目や制度設計のポイントを提示していきます。また、実際の活用事例として、店長評価制度を導入して成功した2つの架空事例をご紹介し、具体的なメリットや運用上の工夫を解説します。
店長職を取り巻く課題と重要性
店長はサロンの顔となるスタイリスト業務を継続しながら、スタッフをまとめたり、売上目標を達成するための施策を考えたりと、多様な責任を負います。一人のプレイヤーであると同時に、「経営者の代理人」としての役割を担うため、以下のような課題が生じやすいです。
- 負荷の高さ: プレイヤー業務とマネジメント業務の両立
- 評価基準の曖昧さ: 店長自身の技術・売上・リーダーシップなど、評価の対象が広範囲
- 客観視の難しさ: 上司(経営者)との距離感が近すぎる場合、評価が主観的になりがち
一方で、店長が正当に評価され、明確なキャリアパスや報酬アップの仕組みがあれば、さらなるモチベーション向上が見込めます。リーダーシップが高まればスタッフ間の結束力も強まり、結果として顧客満足度や売上向上につながるでしょう。その意味で「店長をどう評価し、どう成長を支援するか」は、中小美容業の経営における重要なテーマと言えます。
中小美容業における「店長職」への人事評価制度の導入状況
店長職の評価が後回しにされやすい理由
中小美容サロンでは、現場のトップとして店長が日常的にスタッフを評価する立場にあるため、「店長自身を誰がどう評価するのか」という視点が抜け落ちがちです。加えて、経営者自身がプレイヤーを兼務し、多忙を極める場合、「店長評価まで手が回らない」「なんとなく話し合いで給与を決める」といったケースが多く見受けられます。
また、店長というポジションは、スタイリストとしての技術力や売上実績だけでなく、店舗の収益管理やスタッフ育成、チームビルディングといった幅広いスキルが必要です。このように評価範囲が多岐にわたるため、正当に評価しようとすると時間も手間もかかることから、後回しになりやすいのです。
経営者・人事担当者が感じる評価の難しさ
- 評価項目の複雑性
店長は「プレイングマネージャー」であるため、売上や客単価、施術数などの個人指標に加えて、スタッフマネジメントや在庫管理、コストコントロールなどの管理指標、さらには店舗全体の売上目標達成率や離職率まで見なくてはならず、総合的な評価項目が膨大になりがちです。 - 評価者とのコミュニケーション不足
経営者との距離が近いはずの店長ですが、お互いが現場での施術や管理業務に追われ、定期的な面談やフィードバックが不足しやすい傾向にあります。結果として「店長が普段どのような取り組みをしているか」「経営者がどのような評価基準を重視しているか」がすれ違ったまま評価が行われるおそれがあります。 - 客観的な視点の取り込みが難しい
店長の評価には、スタッフや顧客からのフィードバックも重要ですが、中小美容業では人員や制度が整っていないと、**多面評価(360度評価)**を導入しづらい場合があります。すると、経営者の主観的な印象や店長本人の自己申告に頼りがちな評価になってしまうのです。

2. 店長職の評価が難しい理由とその対策
店長職の人事評価が難しい3つの事情
- 複数の役割を同時に担っている
店長は、スタイリストとしてお客様に施術を提供しながら、シフト作成や備品管理、スタッフ面談や売上管理など多岐にわたる業務を兼任します。評価者は「プレイヤーとしての成果」と「マネージャーとしての成果」の両方を見なければならず、項目が膨大になりがちです。 - 成果が数値化しにくい業務が多い
スタイリストとしての売上や客単価は定量評価しやすいものの、スタッフのモチベーション維持や育成、チームワークの形成といったリーダーシップ面は、成果が目に見えにくく、定量指標も設定しづらいです。 - 評価者自身の主観や曖昧な基準に影響されるリスク
会社規模が小さいと、店長と経営者がほぼ毎日顔を合わせているため、主観的な印象が評価に混ざりやすくなります。日々の運営でトラブルがあれば店長の評価が下がり、順調に回れば店長の評価が上がる、といった曖昧な判断基準が蔓延する危険性もあるでしょう。
課題を解決するための3つの基本アプローチ
- 店長の役割を「プレイヤー」と「マネージャー」に分割して評価項目を整理する
まずは「スタイリスト(技術者)として果たすべき成果」と「店舗管理者として果たすべき成果」を明確に切り分け、それぞれに評価指標を設定しましょう。たとえば、プレイヤーとしては売上や客単価、顧客満足度を測り、マネージャーとしてはスタッフ育成、シフト管理、店舗売上目標の達成度などを検証する形です。 - 定性評価を「具体的な行動や結果」で可視化する
リーダーシップやコミュニケーション力といった定性項目は、抽象的に捉えやすいですが、具体的な行動例をリスト化しておくと評価しやすくなります。たとえば、「スタッフとの定期面談を最低月1回実施し、その内容をレポートにまとめている」「新メニュー導入時に全員へトレーニングを企画し、○回以上の勉強会を行った」など、行動ベースでの記録を求めれば客観性が高まります。 - 評価者と店長の定期的なすり合わせと多角的なフィードバック
店長の評価はどうしても経営者と本人との1対1になりがちですが、可能であればスタッフやエリアマネージャー(存在する場合)からのフィードバックを取り入れる、多面評価に近い形を目指しましょう。最低限、経営者と店長が月1回程度のミーティングや面談を通じ、進捗状況や課題感を常に共有することが不可欠です。
3. 店長職向けの人事評価制度設計ポイント
上記の課題と対策を踏まえ、店長向けの評価制度を設計する際の具体的なポイントを、以下の3つの観点に分けて解説します。
- 定量評価の主要ポイント
- 定性評価の主要ポイント
- 評価結果の活用方法
定量評価の主要ポイント3選
- 店舗全体の売上達成度合い
店長は店舗経営の責任者として、店舗全体の売上目標を達成する義務があります。スタイリスト個人としての売上ではなく、店舗全体の合計売上や平均客単価、新規顧客数、リピート率などを目標指標として設定し、その達成度合いに応じて評価する方法が効果的です。 - 人件費や材料費などのコスト管理
店長は経営者と同じ視点で「利益を出す」ことが求められる立場です。売上が伸びても、人件費や材料費が過剰にかかっていると利益が下がる可能性があります。そこで、経営者と店長で決めた適正な予算枠を守り、コストコントロールを実行できているかを数値化して評価するのも一つの方法です。 - スタッフ離職率・定着率
店長のマネジメント力が高ければ、スタッフ間の人間関係が良好で、離職率が低くなる傾向があります。逆に、店長のリーダーシップが不足していると、スタッフの不満が溜まりやすく退職につながります。したがって、一定期間内の離職率や定着率を指標として設定し、店長がどれだけスタッフのやる気と満足度を高められているかを測ることができます。
定性評価の主要ポイント3選
- リーダーシップ・チームビルディング
店長の重要な役割の一つは、スタッフを率いて目標達成に導くことです。具体的には「定期的なスタッフミーティングの開催」「明確な目標設定と進捗管理」「問題発生時の迅速な対応」など、どのような行動を取っているかを評価項目として挙げると良いでしょう。 - スタッフ育成・教育
美容サロンの成長は、人材の成長に大きく左右されます。店長が「アシスタントの技術研修やスタイリストのスキルアップ」をどのようにサポートしているか、「新人スタッフのメンタルフォロー」などをどれほど徹底しているかなど、育成施策の具体的な実行度を評価できます。 - 顧客満足度向上への取り組み
店長は「顧客満足度を上げる施策」を考え、スタッフと協力して実行する立場でもあります。たとえば、「お客様アンケートの実施と分析」「クレームや要望への迅速な対処」「顧客データ管理と再来店促進施策」など、具体的な取り組みの有無や成果を観察し、定性評価につなげます。
評価結果の活用方法
昇給や賞与だけではなく、キャリアパス構築に活かす
店長評価の結果は、単純に昇給や賞与を決めるだけで終わりにせず、キャリアパス形成の視点でも活用しましょう。将来的に「複数店舗を管理するエリアマネージャー」や「経営幹部」など、さらに上のポジションを用意している場合は、今回の評価結果をもとに「店長としての課題は何か」「どのようなスキルを伸ばせば次のステップに進めるか」を明示すると、店長本人のモチベーション向上につながります。
スキルマップや資格取得支援制度との連動
店長に求められるのはマネジメント力だけではありません。サロン独自の技術認定や、新メニュー導入の際の専門資格取得など、現場のスキルアップが必要なケースも多いでしょう。その場合、店長が「この資格を取得すれば評価アップにつながる」「この研修を受けると管理職としてのスキルが向上し、次の昇進が見えてくる」といった明確な道筋を描けるように、評価制度と研修・資格支援制度を連動させるのが理想的です。

4. 店長職向け 人事評価制度の活用事例
ここからは、店長職に特化した人事評価制度を導入・活用して成果を挙げた、2つの架空事例をご紹介します。実際のサロンでも起こりそうな課題と、その解決策を参考にしてみてください。
事例1
導入背景
地方都市で2店舗を展開する「ヘアサロン・ルーチェ社」は、創業当初から順調に売上を伸ばしてきましたが、2号店を立ち上げて数年が経つと、店長が現場の仕事に追われ、スタッフマネジメントが十分にできていないという問題が顕在化しました。具体的には、シフト管理がずさんで人件費が膨らみ、離職率も上昇。オーナー自身がフォローに回る機会が増え、本業の施術や経営計画に手が回らなくなっていました。
導入内容
- 「プレイヤー評価」「店舗経営評価」を分けた評価シート
店長自身の施術による売上目標(客単価やリピート率など)を「プレイヤー評価」として設定し、店舗全体の売上達成度や人件費コントロール、スタッフ離職率などを「店舗経営評価」として分けて点数化。両方の合計得点で、店長の評価を決める仕組みを導入しました。 - マネジメント行動の可視化
店長が月ごとに行った施策や面談回数、研修実施状況、トラブル対応などを定期的にレポート提出させ、その実行度合いをオーナーが確認。加えて、月1回の面談で「今期はどのようなスタッフ育成を行ったか」「どのコストをどのように削減したか」など具体的な成果をヒアリングし、評価に反映しました。 - エリアマネージャー候補への道筋を提示
ゆくゆくは3店舗目の出店を計画していたため、店長が高評価を得た場合、エリアマネージャーとしての研修や外部セミナーに参加できるように制度設計。数字・行動評価ともに一定基準をクリアすると研修費用を会社が負担するなど、キャリアパスを明確化しました。
導入効果
- 店長がコスト管理を意識するようになり、シフトや在庫管理が改善。不要な残業が減り、1年で人件費が5%ダウン。離職率も従来の2割以上改善。
- 店長がスタッフ育成に時間を割けるようになったことで、アシスタントの技術習得が早まり、全体の売上効率が上昇。
- 高評価を得た店長が外部セミナーに参加し、帰社後に得た知識を共有してチーム全体のスキルアップに貢献。次の出店計画も具体化し始めた。
事例2
導入背景
都内で1店舗を営む「ビューティーサロン・ヒカリ社」は、店長が創業時からのトップスタイリストであり、売上面ではトップクラスの実績を誇っていました。一方で、店長のカリスマ性に頼りすぎた結果、スタッフの意見を吸い上げる仕組みが弱く、若手や中堅スタイリストの育成が停滞。店長とスタッフの間に距離が生まれ、離職も増えてきました。オーナーは「店長としてのリーダーシップ評価を導入し、スタッフ全体を巻き込む文化を作りたい」と考え、評価制度を刷新しました。
導入内容
- スタッフアンケートの活用による多面評価
店長の人事評価に、スタッフアンケート(匿名)を一部反映。質問項目は「店長とのコミュニケーションのしやすさ」「面談の頻度と内容」「サロン方針や目標に対する共有レベル」など、具体的な行動と態度を問う形に設定。アンケート結果の集計はオーナーが行い、評価に10〜20%程度組み込む仕組みを導入。 - リーダーシップ・チームビルディングの指標化
定性評価として、店長が「月1回の勉強会やミーティングを開催し、スタッフの意見を集約して実行する」「新人スタッフに対して週1回以上フィードバック面談を行う」など、行動目標を設定。その達成度合いを、オーナーとの面談で報告するルールを作った。 - 個人売上だけでなく、スタッフの売上成長も評価対象
店長本人の施術売上は高水準だったため、そこだけを評価すると他のスタッフの伸びが軽視される恐れがあった。そこで「店長以外のスタッフの売上成長率」が一定以上なら加点する、という指標を導入し、店長がチーム全体の売上アップに注力できるように工夫した。
導入効果
- スタッフが匿名アンケートで意見を伝えられるようになったことで、店長とスタッフのコミュニケーションが活性化。店長自身も「自分のやり方が独善的だった部分」を客観視し、改善へと動き出した。
- 新人や中堅スタッフへの技術指導や接客指導の質が向上し、1年後には店長以外のスタイリストの売上が平均して15%アップ。サロン全体の売上も右肩上がりに転じた。
- 店長の人事評価に「スタッフ育成」が加わったことで、店長自身もアシスタントや若手スタイリストとのコミュニケーションを強化。サロンの雰囲気が改善し、離職者数が前年より大幅に減少した。
5. まとめ
本コラムのポイント
- 店長職特有の評価項目の設定
店長は「プレイヤー」としての技術売上も評価すべきですが、それだけでは不十分。店舗経営の指標(売上達成率、コスト管理、離職率など)や、リーダーシップ・育成力(スタッフ勉強会、面談などの具体行動)を定量・定性の両面からバランスよく評価する必要があります。 - 明確に区分した評価シートと定期的なフィードバック
店長に求める役割をしっかり言語化し、「何を目指せばどんな評価を得られるのか」を共有することで、店長は自分の行動を客観的に振り返りやすくなります。また、評価者と店長が最低でも月1回の面談やミーティングを行い、進捗や課題を話し合うことで評価のミスマッチを防げます。 - 多角的な視点を取り入れる工夫
スタッフやエリアマネージャー、場合によっては顧客アンケートなどから多角的に店長のリーダーシップやコミュニケーション力をチェックする仕組みを整えると、主観や感情に左右されにくい評価が期待できます。
制度導入・運用における今後のステップ
- 評価制度の継続的な見直し(経営方針・事業規模の変化に合わせる)
店舗数が増える、メニューが拡大するなどで、店長の役割も変わっていきます。少なくとも年1回は評価シートや基準を見直すことで、実態に合った評価制度を維持しましょう。 - キャリアパス制度との連動性を強化して次世代人材の育成
店長職を高く評価し、適切にスキルアップを支援していけば、将来的に「エリアマネージャー」「経営幹部」など、さらに上位のポジションへと成長する人材を確保しやすくなります。店長評価の結果を、今後のキャリアプランにどのようにつなげるかを明確にすると、本人の意欲を高めるでしょう。 - 店長職特有の事情を考慮した人事評価で業績向上を狙う
店長はサロン全体の空気をつくり、経営目標達成を主導する存在です。店長に権限と責任を与えつつ、公正な評価を受ける仕組みを作れば、モチベーション高く仕事に取り組んでくれるはずです。その結果、スタッフ定着率や顧客満足度が高まり、売上・利益の向上へと結びつきます。
店長職への評価制度は、サロン経営を安定化・拡大化するうえで不可欠な要素です。プレイヤーとしての売上貢献だけではなく、スタッフ育成やコスト管理、顧客満足度の向上など、マネージャーとしての手腕をしっかりと可視化し、評価に反映させましょう。これまでの連載で取り上げてきた「アシスタント職」「スタイリスト職」など、各ポジションとの評価制度とも連動させることで、サロン全体の人材育成サイクルを一段と強化できます。
特に、中小美容業では経営者と店長との距離が近いため、定期的な面談や評価プロセスの見直しを意図的に行わないと、曖昧な評価や主観的な印象評価に陥るリスクが高まります。今回紹介した事例やポイントを参考にしながら、ぜひ自社に合った店長評価制度を構築し、サロンの業績向上とスタッフ満足度アップの両立を目指してください。スタッフ全員が気持ちよく働ける環境が整えば、最終的にはお客様の満足度向上にもつながり、サロンのブランド力が向上することは間違いありません。

- 美容院に特化【第1回】| 成功する評価基準と運用ポイント
- 美容院に特化【第2回】| 人事評価制度を導入するメリット、デメリット
- 美容院に特化【第3回】| アシスタント職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第4回】| スタイリスト職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第5回】| 店長職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第6回】| エリアマネージャー職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第7回】| 専門職(アイリスト、ネイリスト)に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第8回】| 効果的な人事評価制度の導入と成功の秘訣