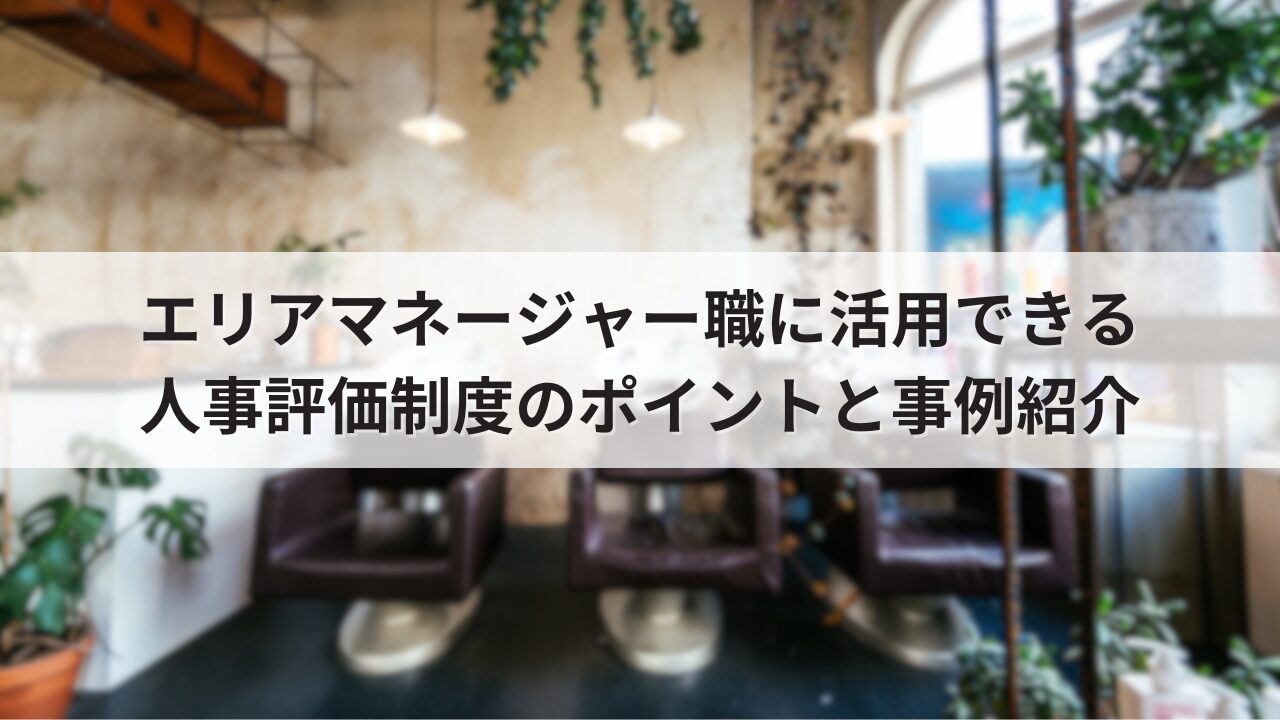- 美容院に特化【第1回】| 成功する評価基準と運用ポイント
- 美容院に特化【第2回】| 人事評価制度を導入するメリット、デメリット
- 美容院に特化【第3回】| アシスタント職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第4回】| スタイリスト職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第5回】| 店長職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第6回】| エリアマネージャー職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第7回】| 専門職(アイリスト、ネイリスト)に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第8回】| 効果的な人事評価制度の導入と成功の秘訣
1. はじめに
本コラムの目的と背景
これまでの連載では、アシスタント、スタイリスト、店長など、各職種の人事評価制度の要点や運用事例を取り上げてきました。中小美容業においては、**「いかに優秀な人材を採用・定着させ、スキルを高めてもらうか」**が大きな経営課題となります。そのために必要なのが、公正で分かりやすい人事評価制度であることは言うまでもありません。
しかし、複数店舗を展開するようになると、エリアマネージャーという新たなポジションが発生します。エリアマネージャーは、店長よりも広い視点で複数店舗の運営をサポート・管理し、経営者が描くビジョンを各店舗に落とし込む役割を担います。店舗が増えるほど、経営者は全店舗を直接管理しきれなくなるため、エリアマネージャーの存在はサロン運営に欠かせないものとなるのです。
本コラムの目的は、エリアマネージャー職特有の課題に着目しながら、どのように人事評価制度を設計すれば、経営者の意図を十分に反映しつつ、エリアマネージャー本人のモチベーション向上と組織成長を実現できるかを解説することにあります。
エリアマネージャー職を取り巻く課題と重要性
エリアマネージャーは、たとえば以下のような重要な役割を果たします。
- 複数店舗の売上目標達成をサポート
- 店長の育成や指導を行う
- 店舗間でのノウハウ共有を推進し、業務効率を高める
- 新メニューやキャンペーンなどの施策を横断的に展開する
- 経営者からの指示や方針を、店舗スタッフに伝達・浸透させる
これらの業務は、店舗ごとの店長とはまた違った次元のマネジメント能力が必要となります。たとえば、売上管理やコスト管理のスケールが大きくなるだけでなく、複数の店長やスタッフと同時にコミュニケーションをとる必要があるなど、管理範囲が格段に広がるのが特徴です。
一方で、エリアマネージャーをどのように評価すればいいのか、悩む経営者や人事担当者は少なくありません。店長職と同様に、プレイヤーとしての売上貢献度を直接測りにくいケースが多いため、評価基準が曖昧になりがちです。しかし、エリアマネージャーが適切に評価され、報酬やキャリアアップが見通せる仕組みが整っていなければ、多店舗展開の要であるこのポジションが長続きしない、というリスクも生まれます。
中小美容業における「エリアマネージャー職」への人事評価制度の導入状況
エリアマネージャー職の評価が後回しにされやすい理由
中小規模の美容サロンでは、最初に店舗が1つか2つしかない段階では、エリアマネージャーという役職自体が存在しないことが多いです。しかし、店舗数が3つ以上に増え、オーナーや経営者だけでは管理が追いつかなくなると、エリアマネージャーの必要性が高まります。
ところが、**「エリアマネージャーを任せる人材を育てる」**というプロセス自体が後回しになり、気づいたら店長が兼任状態になっていたり、「とりあえず店長経験が長いスタッフにお願いしている」という曖昧な形で運用しているケースもあります。その結果、
- 評価制度が店長向けにしか整備されておらず、エリアマネージャーの評価が不十分
- エリアマネージャー本人が自分の役割や目標を明確に把握しておらず、やりがいやモチベーションを感じにくい
といった問題が生じるのです。
経営者・人事担当者が感じる評価の難しさ
- 成果が数値化しにくい
複数店舗の売上管理やスタッフ育成に関与するものの、エリアマネージャー本人が直接お客様に施術を提供するわけではありません。そのため、評価を行う際に「具体的な成果」を可視化しにくく、定量評価と定性評価のバランスをどう取ればいいのか迷いやすいです。 - 責任範囲の広さ
店長であれば1店舗を管理する責任を負いますが、エリアマネージャーは2店舗以上を横断的に管理する必要があります。店舗ごとに異なるスタッフ構成や顧客層、売上目標があり、評価すべき要素が格段に増えるため、評価基準を作るのに手間がかかります。 - 経営者との距離感
エリアマネージャーは経営者の右腕的存在でもあるため、主観的な評価が入りやすい立場です。特に中小企業では、経営者とエリアマネージャーのコミュニケーションが密接になりやすく、その分、「何をどこまで客観的に評価するか」が曖昧になりがちです。

2. エリアマネージャー職の評価が難しい理由とその対策
エリアマネージャー職の人事評価が難しい3つの事情
- 多店舗管理に伴う複雑な指標
売上や客単価、スタッフの離職率、顧客満足度など、一店舗だけを見れば比較的シンプルな指標も、複数店舗を束ねると「どの店舗の成績をどこまで責任範囲として捉えるのか」「店舗間の差異をどう考慮するか」などが問題となります。 - 個人のプレイング要素が薄い
エリアマネージャーは店長と異なり、カットやカラーなどの施術に直接携わるケースが少なく、技術売上で評価することが困難です。どれだけ各店舗を活性化したか、店長の成長を促したかなど、間接的な成果を把握しなければなりません。 - リーダーシップや統率力の評価が主観に偏りやすい
経営者から見て「頼りになるかどうか」「コミュニケーションしやすいかどうか」など、感覚的な印象に左右されやすい面もあります。フェアな評価を行うには、客観的なエビデンスを集める工夫が必要です。
課題を解決するための3つの基本アプローチ
- 店舗ごとの成果指標とエリア全体の指標を明確化する
エリアマネージャーが責任を負う範囲を店舗ごと、あるいはエリア全体で区分し、それぞれに目標値を設定します。たとえば「エリア全体の売上目標」「各店舗の離職率」「新規顧客獲得数」といった指標を用意し、エリアマネージャーのマネジメントによる成果を数値化しやすくします。 - 定性的評価項目を行動レベルまで落とし込む
「リーダーシップ」「コミュニケーション力」「スタッフ育成能力」などの定性的項目を、「○○の勉強会を企画・運営した」「店長との定期ミーティングを月に○回実施している」など、具体的な行動で評価できるよう工夫します。 - 複数の視点を取り入れた評価と定期的なすり合わせ
エリアマネージャーの評価は、経営者だけでなく、店長や他の管理職からのフィードバックも反映させると客観性が高まります。さらに、月次や四半期ごとの面談で目標進捗や課題をすり合わせることで、主観的な評価だけにならないように対策します。
3. エリアマネージャー職向けの人事評価制度設計ポイント
エリアマネージャーの評価制度は、店長やスタイリスト向けの制度とは大きく異なる点があります。それは、「店舗運営やスタッフ育成を、一歩引いた立場からマネジメントする」という点です。ここでは、定量評価と定性評価、それぞれのポイントと評価結果の活用方法を紹介します。
定量評価の主要ポイント3選
- エリア全体の売上目標達成度
もっとも分かりやすい指標の一つが、エリア全体の売上や新規顧客数、客単価などです。たとえば、3店舗の合計月間売上や新規顧客獲得数を目標値と比較し、その達成度合いを評価に加えます。ただし、店舗規模や立地条件に差がある場合は、店舗別の目標や前年対比の伸び率を加味することが望ましいでしょう。 - 店舗別の離職率・スタッフ定着率
エリアマネージャーが店長をしっかりサポートし、スタッフのモチベーションや環境整備に貢献できているほど、離職率は低下しやすくなります。エリア全体としての離職率が目立って高い場合は、何らかのマネジメント上の問題がある可能性が高いため、定量評価に組み込むと良いでしょう。 - コストコントロール(経費削減・材料費管理など)
店舗をまたいでコスト最適化を図るのもエリアマネージャーの重要な役割です。たとえば、材料をまとめて仕入れることでコストを削減したり、無駄な在庫を抱えないよう店舗間で調整するなど、経費管理に関する指標を設定しておくことで、エリアマネージャーが経営的視点を持つインセンティブになります。
定性評価の主要ポイント3選
- 店長の育成・サポート力
エリアマネージャーは、複数店舗の店長を指導・支援し、それぞれの店舗がうまく回るようマネジメントする役割を持ちます。具体的には、「店長との1on1ミーティングを定期的に実施しているか」「トラブル発生時に迅速かつ適切にアドバイスを行っているか」「研修や勉強会を企画しているか」など、行動ベースで評価します。 - 横断的な課題解決・施策立案能力
店長職は店舗単位の課題に取り組みますが、エリアマネージャーは複数店舗に共通する課題(たとえばスタッフ不足、技術力の偏り、接客マニュアルの未整備など)を見つけ、横断的な施策を立案・実行する立場です。こうした「エリア全体の課題を解決する力」を評価項目に含めると、エリアマネージャーらしい動きが促進されます。 - コミュニケーション力・リーダーシップ
エリアマネージャーは、経営者と店長の間に立ち、時にはスタッフや外部の関係者ともやり取りを行う役割を担います。したがって、対人コミュニケーションやリーダーシップが欠かせません。具体的には、「複数の店舗スタッフを集めたミーティングでうまく議論をまとめているか」「新メニュー導入時に店舗間の情報共有をスムーズに行っているか」などを確認します。
評価結果の活用方法
昇給や賞与だけではなく、キャリアパス構築に活かす
エリアマネージャーというポジションは、中小美容業においては「最終的な役職」に見られがちですが、将来的な多店舗展開や新規事業の拡大などを視野に入れると、「本部幹部」や「執行役員」的な立場へとキャリアアップしていく道も考えられます。評価結果を踏まえて、どのようなスキルや実績があれば次のステージへ進めるのか、キャリアパスを提示することで、エリアマネージャー本人の意欲を高めることができます。
スキルマップや資格取得支援制度との連動
エリアマネージャーは、店舗運営だけでなく、人材育成・財務管理・マーケティングなど、多方面の知識とスキルが求められます。会社として、必要なスキルをスキルマップで可視化し、エリアマネージャーが外部セミナーや資格取得を通じて成長できる仕組みを整えると、評価制度と実務スキルの向上がリンクして相乗効果が得られます。

4. エリアマネージャー職向け 人事評価制度の活用事例
ここでは、エリアマネージャー向けの評価制度を導入し、実際に成果をあげた2つの架空事例をご紹介します。実際のサロン運営で起こりやすい課題を踏まえながら、どのように制度を構築・運用すればよいのか、ぜひ参考にしてみてください。
事例1
導入背景
地方都市を中心に4店舗を展開する「ビューティーライフ社」は、経営者が全国規模での出店を考えるほど業績が好調でした。しかし、既存の4店舗のマネジメントが追いつかず、店長間の情報共有不足や人材配置の偏りが目立ち始めました。経営者は「オーナー自身が全店舗を細かく見るのは限界がある」と感じ、既存店長の中から1名をエリアマネージャーに抜擢することにしました。
導入内容
- エリアマネージャー専用の評価シート作成
新たに就任したエリアマネージャーが担当する4店舗について、「エリア全体売上」「店舗別売上」「スタッフ離職率・定着率」「コスト管理」などを定量評価項目に設定。定性評価としては、「店長育成」「横断的課題の解決力」「リーダーシップとチームビルディング」などを含むシートを用意し、月ごとに進捗を確認しました。 - 店長との定期ミーティングとレポート提出
エリアマネージャーが月2回、各店長とのミーティングを行い、その内容を簡潔にレポート化して経営者に提出。課題や施策が可視化されるため、経営者・エリアマネージャー・店長の3者が常に同じ情報を共有できる状態を整えました。これを評価でも重視し、「適切なコミュニケーション・指導を行っているか」をチェックする仕組みを導入。 - 上位職(本部幹部)候補としてのキャリアパス明示
早くも5店舗目、6店舗目の出店計画が進んでいたため、エリアマネージャーが成果を出せば、次の出店時に「より広範囲を管理するマネージャー」や「本部機能の開発担当」としてステップアップできる道が開ける、と明確に提示。評価制度の結果とキャリアアップを連動させることで、エリアマネージャー本人のモチベーションも高まりました。
導入効果
- 店長間の情報共有が活発になり、売れ筋商品の在庫融通やスタッフのヘルプ体制などがスムーズに回るように。結果として、4店舗すべての売上と顧客満足度が上昇傾向に。
- スタッフの離職率が前年同期比で15%減少。エリアマネージャーが店長を支援し、スタッフフォローを徹底できたことが要因として挙げられた。
- 経営者自身が現場の細かなマネジメントから解放され、5店舗目の出店準備や新規事業の検討に時間を割けるようになった。
事例2
導入背景
都心で3店舗を展開する「ヘアサロン・グランデ社」は、競合サロンがひしめくエリアでの生き残りをかけて、差別化戦略として「カット技術の向上」「高級路線のインテリア」「SNSでのブランディング」に力を入れてきました。しかし、店舗間で施策にバラツキが生じ、店長とスタッフがそれぞれ独自のやり方を試すばかりで、経営方針が浸透していないという課題が浮上。そこで、新たにエリアマネージャーを置き、店舗間の連携を強化することにしました。
導入内容
- SNS施策・ブランディングの統括指標を設定
エリアマネージャーが3店舗共通のSNS運用方針(投稿頻度やビジュアルの統一感など)を策定し、店長とスタッフに共有。各店舗のSNSフォロワー数やエンゲージメント率を定量的に把握し、エリアマネージャーの貢献度を見える化しました。 - マーケティングや接客研修の横断的企画
エリアマネージャーが3店舗の店長と協力し、定期的に技術研修や接客セミナーを開催。研修への参加率や、その後の顧客満足度調査での向上度合いを、エリアマネージャーの定性評価に反映するように設計しました。 - 多面評価の一部導入
経営者がエリアマネージャーを評価するだけでなく、店長3名からもエリアマネージャーに対するフィードバックを受け取る仕組みを採用。月1回の店長会議でアンケートを実施し、「連携や情報共有が適切に行われているか」「エリアマネージャーとのコミュニケーションは円滑か」などを確認し、評価に反映しました。
導入効果
- 店舗間で統一的なブランディングやSNS施策ができるようになり、SNS経由の集客率がアップ。フォロワー数の増加に伴って新規顧客の来店が増え、全体売上にもプラス効果。
- 技術研修や接客研修を横断的に行うことで、各店舗が持つ強みを共有し合い、スタッフ間の連帯感が高まる。結果的に、顧客満足度アンケートの平均点が上昇。
- 多面評価を通じて、エリアマネージャーが店長たちの声をダイレクトにキャッチできるようになり、現場で起こっている問題に早く対処可能に。店長たちも「トップダウンだけでなく意見を聞いてもらえる」と感じ、モチベーションが向上した。
5. まとめ
本コラムのポイント
- エリアマネージャー職特有の評価項目の設定
エリア全体の売上、複数店舗のスタッフ定着率、コスト管理、店長育成など、店舗横断的な成果指標を中心に据える必要があります。また、リーダーシップやマネジメント力など定性的な要素も、行動ベースで評価可能な形に落とし込むのがポイントです。 - 評価制度の継続的な見直し(経営方針・事業規模の変化に合わせる)
店舗数が増えれば管理の難易度が上がり、エリアマネージャーに求められるスキルも変化します。定期的に評価項目や目標設定を見直し、実情に合った運用を続けることが大切です。 - キャリアパス制度との連動性を強化して次世代人材の育成
エリアマネージャーは、将来さらに拡大路線を進むサロンにおいて重要なポジションです。評価結果をもとに、「さらに高い役職」「新規事業や新店舗の統括」を担う可能性を示し、本人の成長意欲を高めることで次世代人材を育成できます。 - エリアマネージャー職特有の事情を考慮した人事評価で業績向上を狙う
結局のところ、エリアマネージャーが適切な権限と評価を得られる仕組みが整うほど、経営者は戦略面に集中でき、店長やスタッフも安心して日々の業務に集中できます。エリア全体の運営効率と売上アップを同時に実現するうえで、エリアマネージャーの評価制度は極めて重要と言えるでしょう。
エリアマネージャーの存在は、中小美容業の多店舗展開や組織体制の拡大において、経営の要となります。ただし、その評価制度が曖昧だったり、店長評価制度の単なる延長線上に留まっていると、エリアマネージャー本人も周囲も納得しづらい状況に陥りやすいのが実情です。
そこで本コラムで紹介したように、エリア特有の定量・定性評価項目をしっかり整理し、キャリアパス制度や研修制度とも連動させながら、適切なインセンティブを与えることが欠かせません。さらに、評価者(経営者)とエリアマネージャー、そして店長やスタッフなど多角的な視点を取り入れた評価プロセスを定期的に回すことで、双方の目線がずれにくい環境を作れます。
今後、さらに店舗数が増えたり、新しい施策や事業領域にチャレンジする際には、エリアマネージャーの役割も変化していく可能性が高いでしょう。そのたびに評価制度を見直し、スキルマップを更新し、本人とのコミュニケーションを重ねることで、「エリアマネージャーが経営者とともにサロンを盛り立てる」体制が築かれます。人事評価制度は作って終わりではなく、組織の成長に合わせて常にアップデートしていくものという認識を持ち、ぜひ継続的な運用に努めてください。
適切に評価されるエリアマネージャーが育てば、店長やスタッフの育成・支援が強化され、結果的にはサロン全体の業績向上とブランド力向上につながります。中小美容業が生き残り、さらに飛躍するための大きなカギが、このエリアマネージャー評価制度にあると言っても過言ではないでしょう。今回の内容を参考に、自社の規模や経営戦略に合わせた評価制度の導入・改善を検討してみてください。

- 美容院に特化【第1回】| 成功する評価基準と運用ポイント
- 美容院に特化【第2回】| 人事評価制度を導入するメリット、デメリット
- 美容院に特化【第3回】| アシスタント職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第4回】| スタイリスト職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第5回】| 店長職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第6回】| エリアマネージャー職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第7回】| 専門職(アイリスト、ネイリスト)に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 美容院に特化【第8回】| 効果的な人事評価制度の導入と成功の秘訣