-
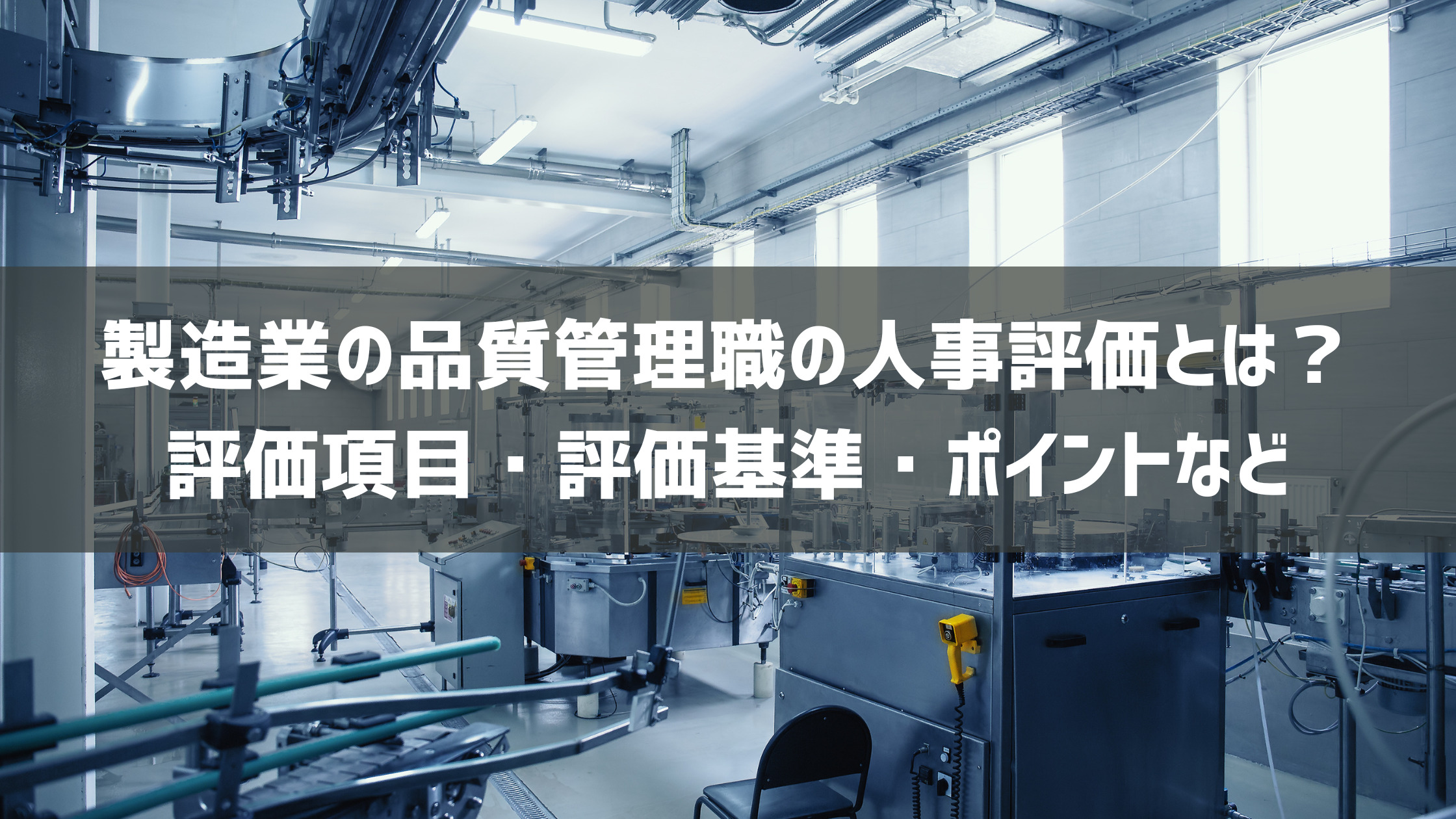
製造業の品質管理担当職の人事評価とは?評価項目・評価基準・ポイントなど
-

クリニック向け!効果的な人事評価制度の導入と成功の秘訣
-

保育園に特化 | 効果的な人事評価制度の導入と成功の秘訣
-
職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介.jpg)
保育園に特化 | 専門職(調理師、管理栄養士)職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
-
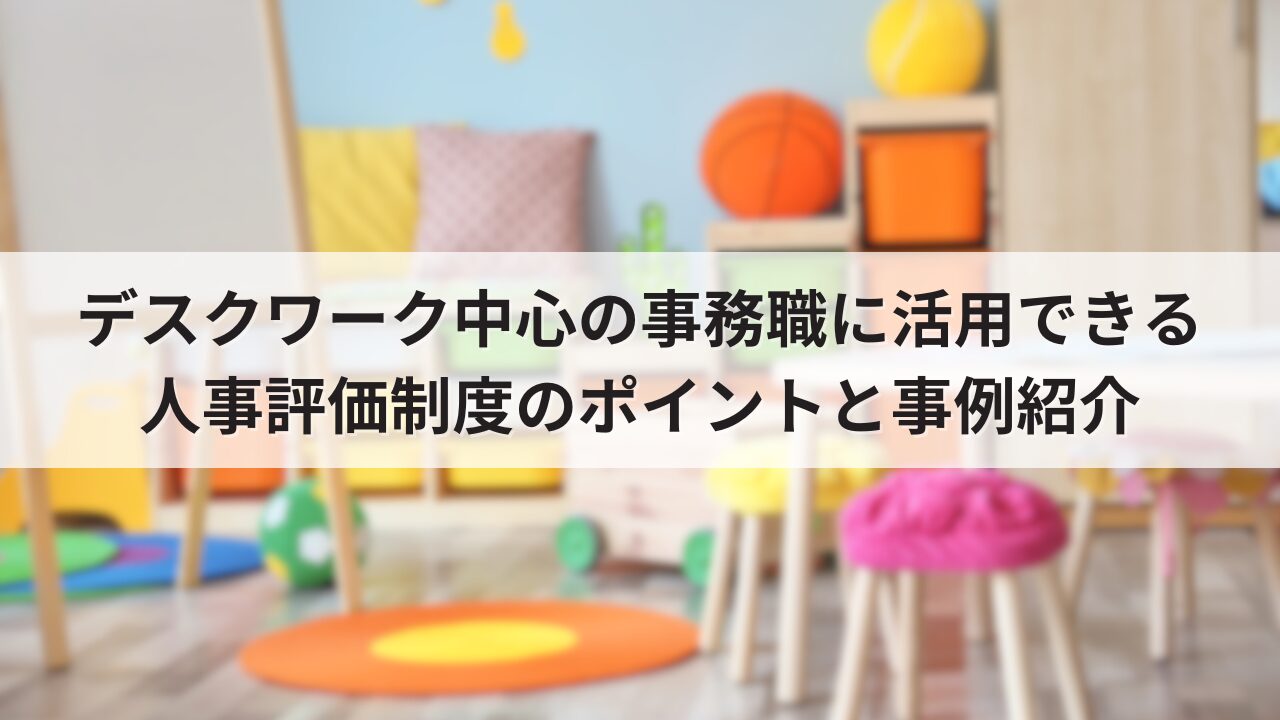
保育園に特化 | デスクワーク中心の事務職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
-
に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介.jpg)
保育園に特化 | 管理職(園長、副園長)に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
-
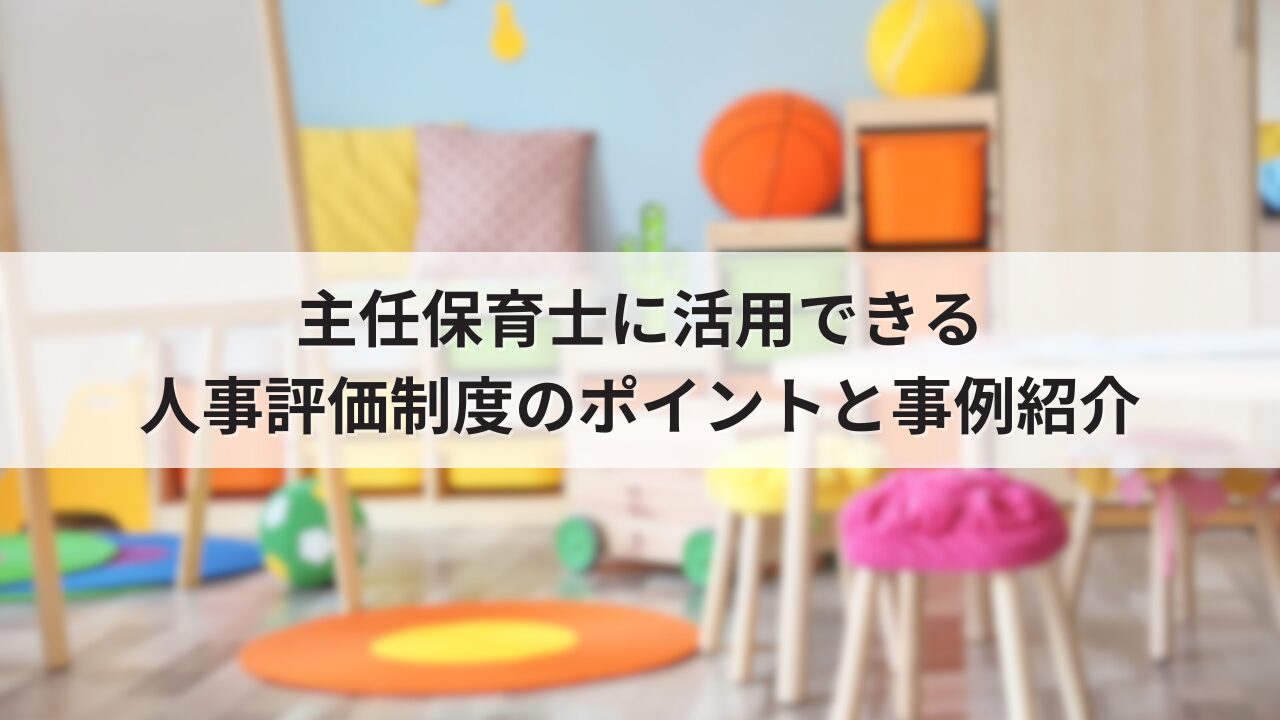
保育園に特化 | 主任保育士に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
-
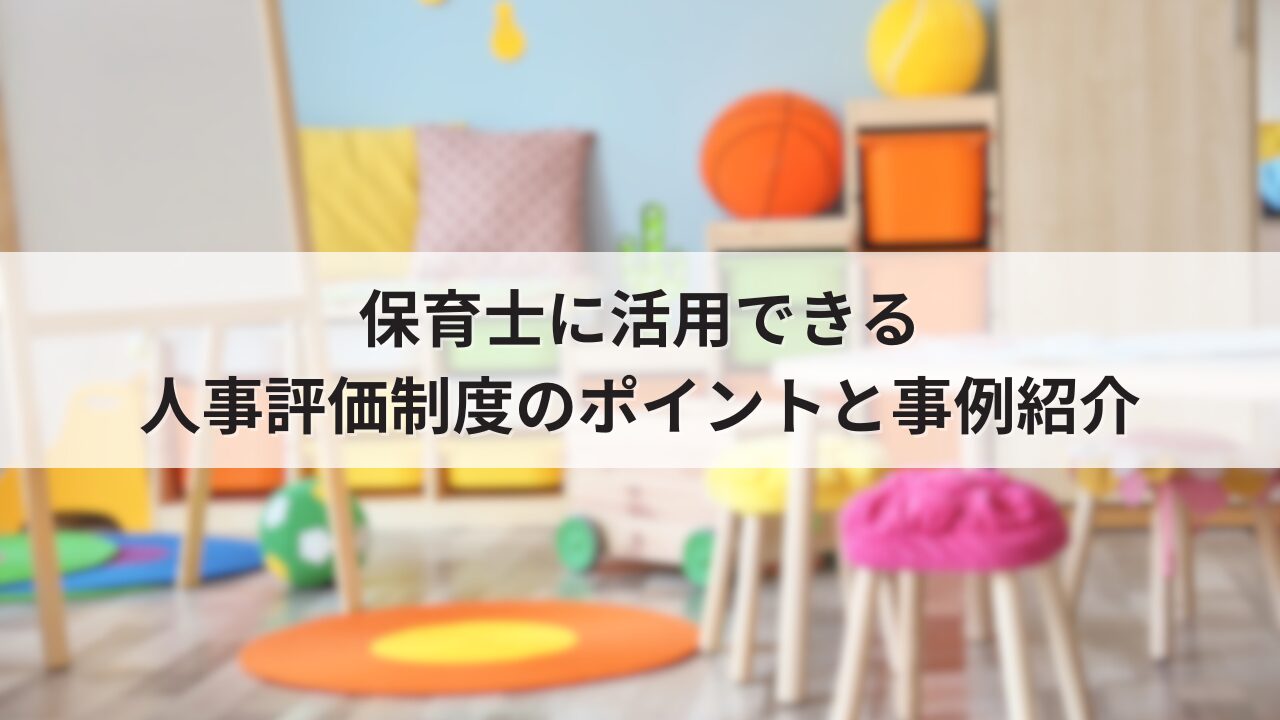
保育園に特化 | 保育士に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
-
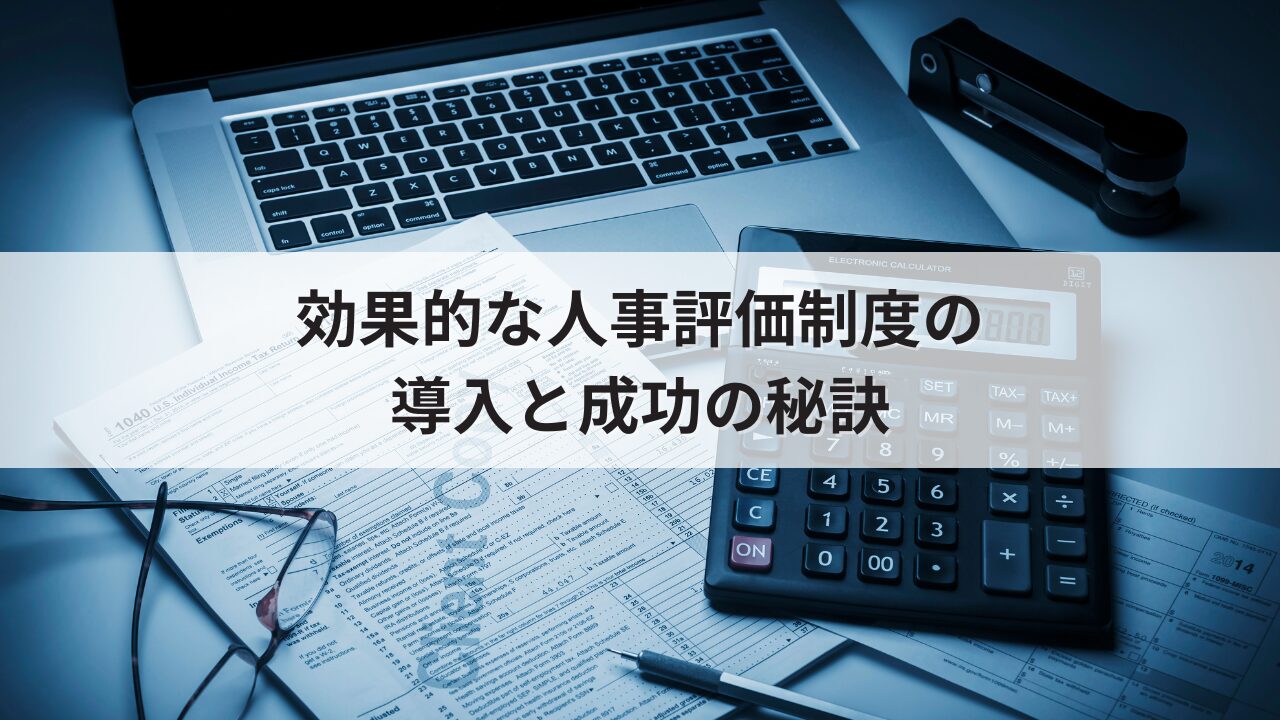
税理士事務所に特化 | 効果的な人事評価制度の導入と成功の秘訣
-
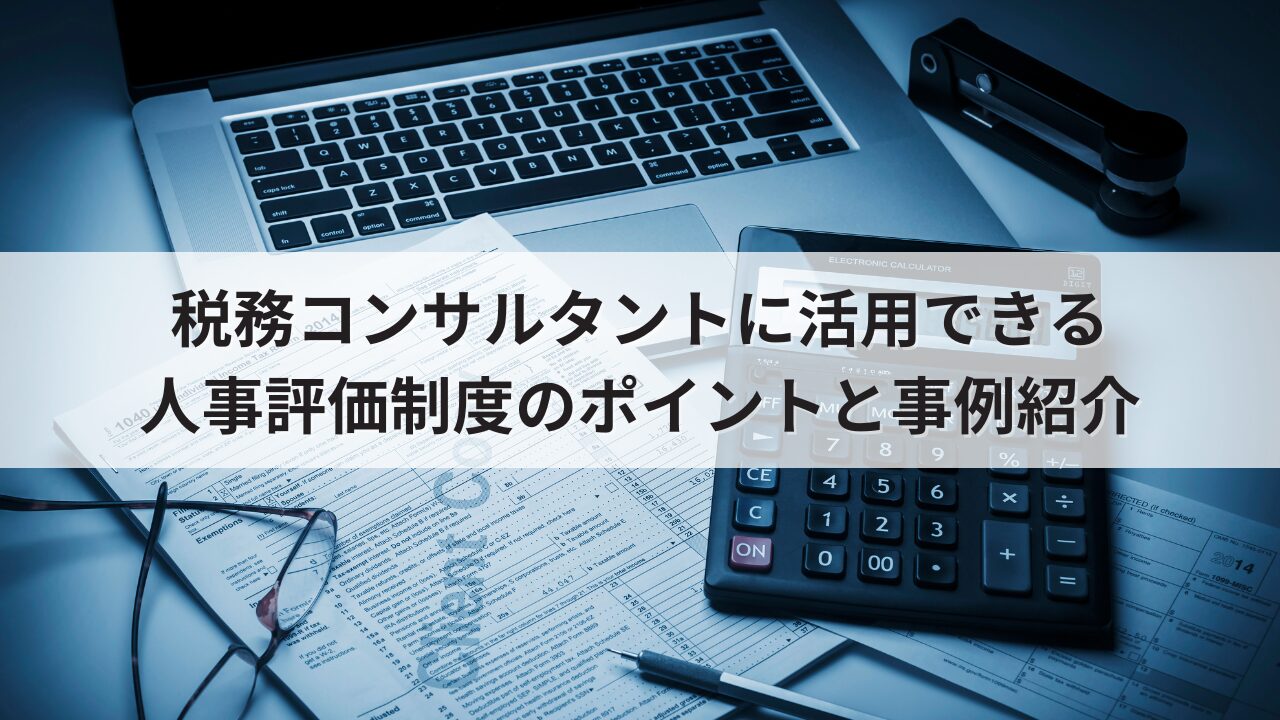
税理士事務所に特化 | 税務コンサルタントに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介

