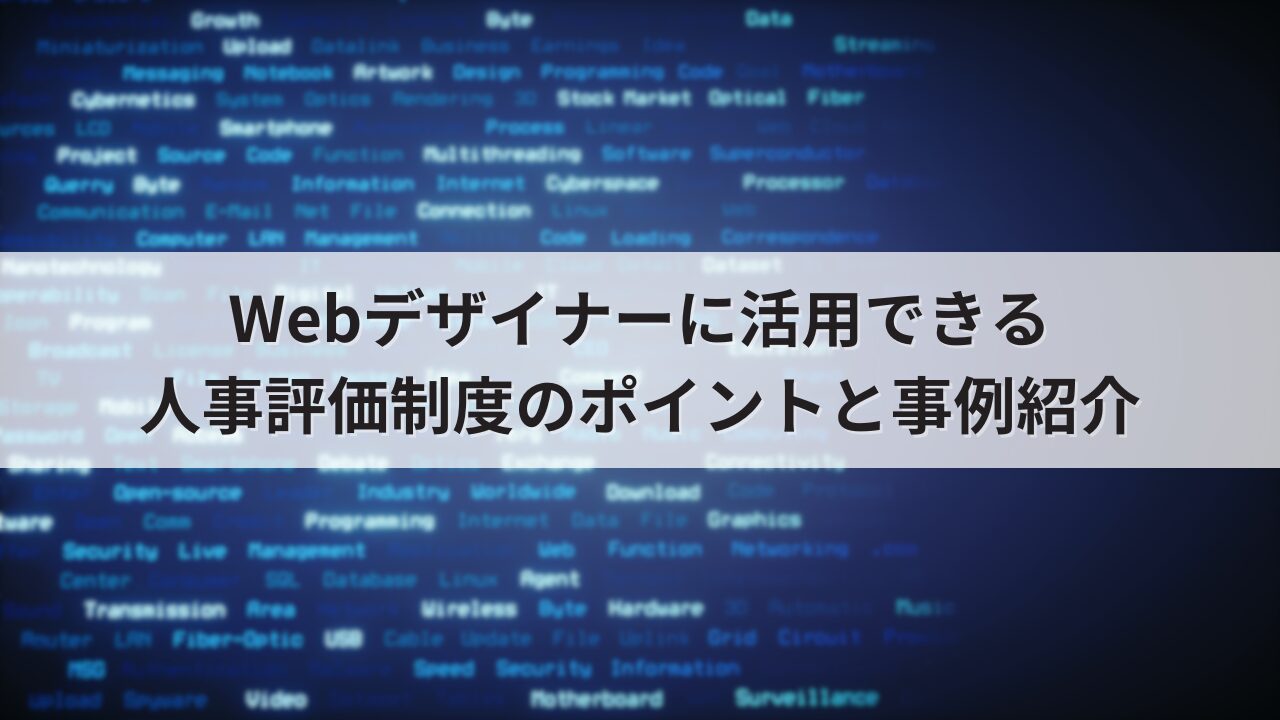- IT業に特化【第1回】| 成功する評価基準と運用ポイント
- IT業に特化【第2回】| 人事評価制度を導入するメリット、デメリット
- IT業に特化【第3回】| プログラマーに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第4回】| システムエンジニアに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第5回】| プロジェクトマネージャーに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第6回】| Webデザイナーに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第7回】| ITコンサルタントに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第8回】| 効果的な人事評価制度の導入と成功の秘訣
1. はじめに
本コラムの目的と背景
これまでの連載コラムでは、IT業界が抱える人事評価制度の難しさと、職種ごとのポイントを解説してきました。IT業界では技術革新やプロジェクト形態の多様化が進む一方、企業ごと・職種ごとに評価の在り方が大きく異なるため、**「一律の評価制度では人材のモチベーションや適正を十分に引き出せない」**という課題が浮き彫りになっています。
今回のテーマである「Webデザイナー」は、IT業界の中でもUI/UX設計やクリエイティブ面を担う重要なポジションです。Webサイトのデザインだけでなく、スマホアプリや各種デジタルプロダクトに関わることもあり、企業やサービスの“顔”をつくり出す立場にあります。しかし、Webデザイナーの評価基準を明確に定めている中小IT企業は、まだまだ多くありません。
- デザインの良し悪しが主観的な判断に左右されがち
- クライアントの要望に左右され、企業として何を評価すべきかが曖昧
- 制作物の成果(売上やアクセス数)とデザイナー個人の能力をどう紐づけるか
こうした状況を踏まえ、本コラムではWebデザイナーの評価がなぜ難しいのか、どのように評価制度を設計すれば良いのかを中心に解説していきます。
Webデザイナーを取り巻く課題と重要性
Webデザイナーの仕事は、「美しく魅力的なデザインを作る」というだけでは済みません。ユーザー体験(UX)の向上を考慮し、コーディングやディレクション、時にはマーケティング面まで踏み込んで提案するケースも増えています。また、デバイスやプラットフォームの多様化に伴い、デザインツールやプロトタイピングツールなど、求められるスキルセットも日々アップデートが必要です。
- 企業ブランドやサービス価値を、視覚的にわかりやすく伝える要の職種
- ユーザーにとって使いやすく魅力的なUI/UXを設計することで、顧客満足度や売上増に貢献
- フロントエンドの基本知識やディレクション能力があれば、プロジェクト全体を牽引する役割も担える
このように、Webデザイナーはビジネスに直結するクリエイティブを生み出す存在として非常に重要です。そのため、適切な評価制度を整えることは、デザイナーのモチベーションと企業の収益向上の双方に効果をもたらすでしょう。
中小IT業における「Webデザイナー」への人事評価制度の導入状況
Webデザイナーの評価が後回しにされやすい理由
中小IT企業では、プログラマーやシステムエンジニアと比べて、Webデザイナーを評価する仕組みや指標が整っていないケースが散見されます。理由としては以下のような点が挙げられます。
- デザインの評価が主観に寄りがち
デザインは数値化しづらく、担当者や経営者の好みで判断されがちなため、客観的な基準を設けにくい状況があります。 - 制作プロセスが分かりにくい
プログラムの開発工程はタスク管理ツールなどで可視化しやすいのに対し、デザインの工程は「アイデアの発想」「試作と修正」の繰り返しが多く、どこにどれだけ時間がかかったか把握しづらい場合があります。 - 売上との結びつきが曖昧
開発案件の場合、「機能リリース→売上貢献」という流れが比較的分かりやすいですが、デザインはサイトやサービス全体の一部として評価されるため、直接的な数値成果に結びつけづらい側面があります。
経営者・人事担当者が感じる評価の難しさ
- 「センス」をどう評価すればいいのか分からない
- クライアントの要望通りに仕上げても、自社としては物足りない…どこまで加点・減点すべき?
- UI/UXの改善が最終的に売上アップに繋がっているかどうかを測りづらい
- コーディングも行うデザイナーと、ビジュアル専門のデザイナーでは評価基準に差が出る
こうした課題に対処するためには、Webデザイナーの仕事における**「定量面」と「定性面」**をバランスよく評価に織り込む必要があります。

2. Webデザイナーの評価が難しい理由とその対策
Webデザイナーの人事評価が難しい3つの事情
- 主観的な美的評価が中心になりやすい
デザインの良し悪しは、ビジュアルの印象やセンスに依存する部分があり、採用する側も評価する側も「なんとなく良い」または「なんとなく悪い」となりがちです。数値や指標を用いないと、「上司や経営者の好み」で評価が左右される危険があり、公平性を保つのが難しくなります。 - ビジネス成果との紐づけが複雑
Webデザイナーの成果は、サイト訪問者の離脱率低下やコンバージョン率向上、ユーザーの満足度向上などに貢献する一方、それらの成果はマーケティング施策やサイトのコンテンツ内容、他メンバーの開発など多くの要因が絡み合って生まれるものです。そのため、デザイナー個人の力がどこまで貢献したのかを切り分けるのが難しい面があります。 - 作業プロセスが可視化されにくい
デザインプロセスには、リサーチやラフ作成、プロトタイプ、修正などの工程が含まれます。しかしこれらの工程はスピードや工数を管理するツールで把握しにくく、**「どの工程にどれだけ時間をかけ、どのような試行錯誤を経たか」**が評価者に伝わりにくいのが現実です。
課題を解決するための3つの基本アプローチ
- 定量評価と定性評価を組み合わせる
単に「デザインが良いか悪いか」という曖昧な尺度ではなく、**「コンバージョン率」「UI改善前後の離脱率」「ユーザーテストやヒアリングでの満足度」**など数値化できる要素を取り入れると客観性が増します。一方で、コミュニケーション能力やクリエイティブ発想力、チーム貢献度などは定性評価でフォローし、バランスを取ることが大切です。 - 業務プロセスの可視化とレビュー制度の導入
デザインの制作過程をタスク管理ツールやプロジェクト管理ツールでこまめに記録し、ラフ案やプロトタイプを定期的にレビューする仕組みを設けると、評価者が「どのようにデザインが形作られていったか」を把握しやすくなります。定期レビューを通じてのフィードバックがそのまま評価の根拠にもなり、公平性や納得感が高まるでしょう。 - UI/UXの数値指標を積極的に活用する
Googleアナリティクスやヒートマップツール、A/Bテストなどを活用すれば、デザイン変更の効果を数値で把握できます。たとえば「新しいLPデザインにした結果、問い合わせ数が20%増加した」といった具体的成果が得られれば、デザイナーの貢献度をより正確に評価できるようになります。
3. Webデザイナー向けの人事評価制度設計ポイント
以下では、Webデザイナーを評価する際に活用できる具体的な「定量評価」と「定性評価」の指標、そして評価結果の活用方法を紹介します。デザイナー特有の創造的な業務をどう客観的に評価し、かつモチベーション向上やキャリア形成につなげるかがポイントです。
定量評価の主要ポイント3選
- KPI指標(コンバージョン率・離脱率・アクセス解析)
Webサイトやランディングページをデザイン・リニューアルした結果、コンバージョン率がどの程度上がったか、あるいは離脱率がどの程度下がったかは大きな定量指標になります。クライアントワークの場合は「クライアントの要望に応じてKPIが達成できたか」を確認するのも効果的です。ただし、マーケティング施策や広告運用など他の要因も影響するため、あくまで「デザイナーが担った役割の範囲での貢献度」を評価する必要があります。 - 制作工数・スケジュール遵守率
デザイナーの作業スピードや納期管理に注目する方法です。特にクライアント案件の場合、スケジュールを守れるかどうかは企業の信頼にも直結します。デザイン案のクオリティを維持しつつ、提案から制作、修正対応までを円滑に進められたかを数値化・可視化すると、客観的評価に役立ちます。 - コストパフォーマンス(外注比率・ツール活用度など)
デザイナーが高度なスキルを持っているほど、外注に回さずに社内で完結できる作業が増え、結果的にコスト削減につながる場合があります。また、FigmaやSketchなどのデザインツールを効率的に使い、プロトタイピングの時間を短縮したり、開発との連携をスムーズに進めたりする能力も評価対象になるでしょう。
定性評価の主要ポイント3選
- クリエイティブ発想力・デザインの独自性
数値だけでは測れない**「独創的なアイデア」「デザインの完成度」「最新トレンドのキャッチアップ能力」**などを評価する項目です。曖昧になりがちなため、評価者とデザイナーの間で「参考としたトレンドサイトやデザイン事例」「ユーザーリサーチの内容」を共有しながら議論すると、より客観性を保ちやすいでしょう。 - コミュニケーション・チーム貢献度
デザイナーはクライアントの要望を正確に汲み取りつつ、開発チームとの連携を密にしてデザインを実装に落とし込む必要があります。ミーティングでの発言や調整力、他メンバーへのデザイン意図の説明、ドキュメント整備といった行動面を評価項目として設定すると、チーム全体で成果を出すための姿勢を促進できます。 - UI/UXへの配慮・ユーザビリティの改善
見た目の美しさだけでなく、ユーザビリティ(使いやすさ)やアクセシビリティを考慮したデザインができているかを確認する項目です。たとえば、「ユーザーテストやヒアリングの結果を踏まえて改善を提案した」「アクセシビリティ基準(WCAGなど)を意識した配色やコントラストを設定している」などの行動を定性的に評価します。
評価結果の活用方法
昇給や賞与だけではなく、キャリアパス構築に活かす
Webデザイナーのキャリアパスは多様です。**アートディレクター、UI/UXデザイナー、フロントエンドエンジニア寄りの職種、デザインディレクター(PM的立場)**など、スキルや志向性によって進める道が広がります。評価制度の中で、「どの指標で高評価を得るとどのキャリアに進みやすいか」を可視化すると、デザイナー本人が将来像を描きやすくなります。
- アートディレクター:クリエイティブ発想力、トレンドキャッチアップ能力が高い
- UI/UXスペシャリスト:ユーザビリティ検証やリサーチ力が優れている
- フロントエンドエンジニア:コーディングスキルや開発チームとの連携が得意
- ディレクター/PM:コミュニケーション力やマネジメント思考が高い
評価面談で「あなたの強みはここだから、この道を伸ばしていこう」「次はこういう案件で実績を積んでみよう」と提案できれば、デザイナーのモチベーションを維持・向上させやすくなります。
スキルマップや資格取得支援制度との連動
Webデザイナーが取り組むべきスキルは、PhotoshopやIllustratorといったグラフィックツールから、HTML/CSS/JavaScriptなどのフロントエンド、UI/UX設計論、マーケティング知識まで多岐にわたります。スキルマップを作成し、各領域での習熟度を可視化することで、**「いま足りないスキル」「これから重点的に学ぶべきスキル」**を明確にできます。
また、資格取得支援制度を整えて、Adobe系の認定資格やWebデザイン技能検定、UI/UX関連の認定プログラムなどを評価項目に加点する仕組みを導入すれば、個々のデザイナーが積極的に自己研鑽を行うインセンティブが働きます。これにより、組織全体のデザイン水準が底上げされることも期待できます。

4. Webデザイナー向け 人事評価制度の活用事例
ここでは、実際にWebデザイナー向けの評価制度を導入し、企業として成功を収めている2つの事例を紹介します。企業規模やプロジェクト内容が異なるケースですが、評価項目や運用方法に工夫を施すことで、デザイナーのモチベーションを高め、ビジネス成果にも繋げている点が参考になるでしょう。
事例1
導入背景
- 企業規模:社員数約20名(Webデザイナーは3名)
- 主な事業:中小企業向けのコーポレートサイト制作と運用保守
- 課題:デザイナーの評価が代表取締役の主観に大きく依存しており、**「なんとなく良い」「もう少し派手に」**といった曖昧なフィードバックしか得られない状況だった。デザイナー同士の不公平感も募っていた。
導入内容
- コンバージョン指標の導入
クライアントサイトの目的(問い合わせ数増加、資料請求、EC購入など)に応じてKPIを設定し、リニューアル後の成果を定量評価に反映。デザイナーが提案したデザインによってCVR(コンバージョン率)がどの程度上がったかを数値で追跡する仕組みを整えた。 - デザインレビュー会の定期開催
毎週1回、進行中のデザイン案をチームでレビューしあう場を設け、良い点や改善点を具体的にフィードバックし合う。代表取締役だけでなく、プログラマーや営業担当も参加することで、さまざまな視点からデザインの品質や納期をチェック。フィードバック内容を評価シートに簡単に記録し、最終評価時の参考にした。 - 定性評価:チーム貢献度や顧客折衝力を可視化
デザイナーがクライアントと直接コミュニケーションを行う機会が増えたため、**「顧客の要望を的確にヒアリングし、適切な提案を行ったか」**などの行動評価項目を設定。リードデザイナーが面談時にヒアリングを行い、具体例を挙げながら点数を付ける方式にした。
成果
- これまで「主観に左右されている」と感じていたデザイナーたちが、数値指標やレビュー会を通じてより客観的な評価を得られるようになり、納得度が高まった。
- デザインレビュー会でノウハウや技術が共有され、全体的なデザインスキルが底上げされた。
- 結果的にクライアントの満足度も上がり、リニューアル後のCVR向上事例が増加。新規案件の獲得にも繋がった。
事例2
導入背景
- 企業規模:社員数約50名(Webデザイナーは7名)
- 主な事業:Webアプリ開発と、自社メディア運営
- 課題:自社メディアやクライアント案件で複数のデザイナーが並行して作業するなか、**「誰がどの部分を担当しているのか」「どれだけ時間をかけているのか」「成果にどれほど貢献しているのか」**が不透明。さらに、デザイン改修の効果をきちんと測定する仕組みがなく、デザイナーの評価が曖昧になっていた。
導入内容
- プロジェクト管理ツール+デザインプロセスの可視化
RedmineやJiraといったツールを用いてタスクを細分化し、**「ワイヤーフレーム作成」「プロトタイプ作成」「UIパーツ作成」**など工程ごとに担当者と予定工数を明確化。デザイナーがタスク完了時に実工数を記録することで、プロセスの見える化を図った。 - UI/UX改善効果の定量化
自社メディア上でのデザイン変更やABテストを積極的に行い、ページビュー・滞在時間・クリック率・コンバージョンなどの指標を管理。デザイン変更前後の数値差分をレポート化し、デザイナー個人の貢献度を可視化した。クライアント案件でも同様にAnalyticsを用いて成果を追跡。 - スキルマップを用いたキャリア面談
7名のデザイナーに対して、グラフィックツール、UI/UX、フロントエンド、ディレクションなど複数スキル領域を横軸にとったスキルマップを作成。面談で本人の習熟度を話し合い、「UI/UX分野をさらに伸ばしたい」「ディレクション能力を強化したい」などのキャリア志向をヒアリングし、評価結果や資格取得支援制度と結びつけた。
成果
- プロセス管理によって、どのデザイナーがどの工程に強みを持っているかが明確になり、プロジェクトアサインの最適化が進んだ。
- デザイン改修の効果を数値で共有する文化が根付き、定量的な成果が高いデザイナーは昇給や重要案件への配属機会が増えるなど、モチベーション向上に繋がった。
- スキルマップに基づくキャリア面談を実施することで、デザイナー自身も将来像を具体的にイメージしやすくなり、離職率が低下した。
5. まとめ
本コラムのポイント
- Webデザイナーは、企業やサービスの“顔”となるクリエイティブを担う重要職種だが、主観や外部要因に左右されやすいため、評価が曖昧になりがちである。
- 定量・定性の両面から評価基準を設定し、制作プロセスの可視化やデザインレビュー、UI/UX指標の活用などを行うと、より公平・客観的な評価が可能になる。
- 評価結果を単なる昇給・賞与だけで終わらせず、キャリアパス(アートディレクター、UI/UXスペシャリストなど)の提示やスキルマップとの連動によって、デザイナーの成長意欲や定着率を高められる。
制度導入・運用における今後のステップ
- 評価制度の継続的な見直し(経営方針・事業規模の変化に合わせる)
Webデザインのトレンドやツールは常に進化しているため、評価基準も定期的にアップデートする必要があります。企業の方針転換や取り扱い案件の変化にあわせ、新たなスキルや成果指標を追加していきましょう。 - キャリアパス制度との連動性を強化して次世代人材の育成
Webデザイナーが将来どんな役割を担いたいのかを明確にするために、アートディレクターやUXリサーチャー、ディレクターなどの道筋を示すとともに、それぞれの職種に必要なスキルセットや成果基準を紐づけることが大切です。 - Webデザイナー特有の事情を考慮した人事評価で業績向上を狙う
デザインの質がユーザー体験や売上にも直結する現代では、Webデザイナーの能力を最大限に引き出し、継続的にスキルアップを支援することが企業の業績向上に大きく貢献します。適正な評価制度を整えれば、デザイナー本人も会社に対して愛着を持ち、クリエイティブの向上に全力を注ぐようになるでしょう。
今回のコラムでは、Webデザイナーに特化した人事評価制度のポイントを取り上げました。ビジュアルやセンスといった主観的な要素だけではなく、UI/UX改善やコンバージョン最適化など客観的な数値指標も活用することで、評価の透明性と納得感を高める方法をご紹介しました。前回までのコラム(プログラマー、システムエンジニア、プロジェクトマネージャーなど)の内容とあわせてお読みいただき、各職種を総合的に評価する仕組みを構築する一助になれば幸いです。
今後もIT業界は多様化・高度化が進み、デザイナーの役割も広がっていくことが予想されます。ぜひ自社の状況に合わせた評価制度を柔軟に設計し、Webデザイナーが持つクリエイティブ力を存分に活かせる組織づくりを目指してみてください。
- IT業に特化【第1回】| 成功する評価基準と運用ポイント
- IT業に特化【第2回】| 人事評価制度を導入するメリット、デメリット
- IT業に特化【第3回】| プログラマーに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第4回】| システムエンジニアに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第5回】| プロジェクトマネージャーに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第6回】| Webデザイナーに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第7回】| ITコンサルタントに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第8回】| 効果的な人事評価制度の導入と成功の秘訣