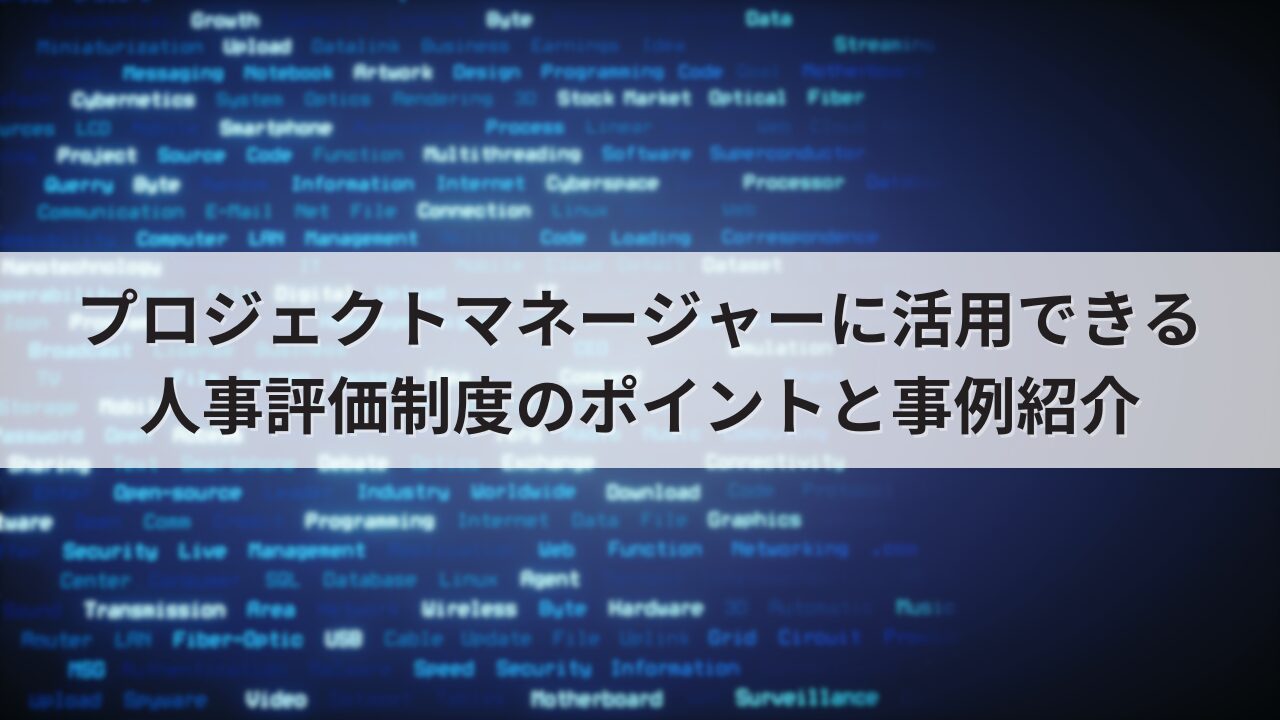- IT業に特化【第1回】| 成功する評価基準と運用ポイント
- IT業に特化【第2回】| 人事評価制度を導入するメリット、デメリット
- IT業に特化【第3回】| プログラマーに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第4回】| システムエンジニアに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第5回】| プロジェクトマネージャーに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第6回】| Webデザイナーに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第7回】| ITコンサルタントに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第8回】| 効果的な人事評価制度の導入と成功の秘訣
1. はじめに
本コラムの目的と背景
これまでの連載では、主に中小IT企業が抱える人事評価制度上の課題や、職種特有の評価ポイント(プログラマーやシステムエンジニアなど)を解説してきました。IT業界は技術やプロジェクト形態が多様化・高速化しており、職種ごとに求められるスキルや役割が異なるため、全員を一律の基準で評価するのは難しいのが実情です。
今回着目するのは、プロジェクト全体を統括し、進捗管理・品質管理・コスト管理・リスク管理など、多岐にわたる責任を担う「プロジェクトマネージャー(PM)」です。PMの働き次第でプロジェクトの成否が左右されるため、企業にとって非常に重要なポジションと言えます。一方で、その重要度に反して**「具体的に何を評価すべきか分からない」「成功も失敗も外的要因が絡み合い、個人評価が曖昧になる」**などの課題が挙げられます。
そこで本コラムでは、PM特有の課題を整理しながら、人事評価制度の設計・運用において押さえておきたいポイントを紹介します。さらに、実際にPM向けの評価制度を導入した中小IT企業の事例も取り上げますので、皆さまの会社での制度づくりや見直しのヒントになれば幸いです。
プロジェクトマネージャーを取り巻く課題と重要性
PMの役割は多様ですが、大きく下記のような点で企業経営に大きく貢献します。
- プロジェクトの進捗を管理し、納期と品質を担保する
ITプロジェクトでは、納期の遅延や不具合が業績に直結するケースが多々あります。PMがしっかりと管理し、問題を未然に防いだり、早期にリスク対応したりすることで、企業の信頼や利益を守ることができます。 - チームをまとめ、人材育成にも寄与する
PMは開発チームやデザイナー、他部署などを取りまとめ、コミュニケーションハブとして機能します。若手や中堅社員の成長を支援したり、適切な役割分担を行ったりすることで、組織全体のスキルアップと定着率向上に寄与します。 - 顧客折衝力や提案力が企業の収益拡大を左右する
受託開発の場合、PMが顧客と直接やり取りし、要望や仕様変更をまとめ上げることも少なくありません。うまく追加提案を行い、新たな売上につなげるスキルは、企業経営の観点から見ても非常に価値が高いです。
このように、PMは企業の“収益面”と“組織力強化”の両面で大きな役割を果たします。逆に言えば、PMの評価制度が機能していないと、優秀な人材が正しく報われずに離職したり、プロジェクトの失敗リスクが増大したりしかねません。
中小IT業における「プロジェクトマネージャー」への人事評価制度の導入状況
プロジェクトマネージャーの評価が後回しにされやすい理由
中小IT企業では、PMを専任で置かずにリーダー的な役割をエンジニアやシステムエンジニアが兼任するケースが見られます。そのため、PMの責任範囲が曖昧になり、評価基準が不透明なまま運用されがちです。さらに、経営層が「とりあえずプロジェクトが無事に納品されれば良い」という意識にとどまると、PM個人のマネジメント能力やチーム育成力が正当に評価されないこともあります。
また、PMという役割は**プロジェクトの外部環境(顧客の都合、他部署のリソース状況など)**に大きく左右されるため、成果や失敗が個人の能力だけによらない面が強く、評価を難しくしている要因の一つでもあります。
経営者・人事担当者が感じる評価の難しさ
- PM個人のスキルでコントロールできる部分と、外的要因の切り分けが難しい
- 定量評価だけでは測りきれないコミュニケーション能力やリーダーシップなどをどう扱うか
- プロジェクトごとに予算や期間、難易度が異なり、単純比較ができない
- 兼任PMが多く、どこからがPM業務なのかが曖昧になりがち
このような悩みを解決するには、まずはPMに求められる役割や成果を明確化し、それを複数の指標(定量・定性)で評価する仕組みを整える必要があります。

2. プロジェクトマネージャーの評価が難しい理由とその対策
プロジェクトマネージャーの人事評価が難しい3つの事情
- 成果が“数字”だけに現れにくい
プログラマーやデザイナーといった個別の成果物と異なり、PMはプロジェクト全体を俯瞰してマネジメントします。そのため、「どれだけバグを減らしたか」「新機能をいくつ実装したか」という定量化がしにくく、チーム全員の成果と個人の貢献が混ざり合うケースが多いです。 - プロジェクト難易度や外部要因の影響が大きい
大規模で複雑なプロジェクトほどリスクも増え、PMの負担やスキル要求が高まります。一方で、顧客都合で仕様が頻繁に変わるなど、PMではコントロールしきれない外部要因も存在します。こうしたプロジェクトごとの違いをどう評価に加味するかが難しくなります。 - コミュニケーション・リーダーシップなど定性的なスキルが中心
PMには進捗管理やコスト管理といった定量的指標だけでなく、チームビルディング、トラブルシューティング、顧客折衝力などのヒューマンスキルが求められます。これらを客観的に測る方法が十分に整備されていない企業では、評価が主観的になりがちです。
課題を解決するための3つの基本アプローチ
- 複数の指標を組み合わせて総合評価する
プロジェクトの予算や納期遵守率といった定量評価だけではなく、チームメンバーや顧客、経営陣からのフィードバックを取り入れた定性評価を組み合わせることで、PMの貢献を多角的に捉えられます。**「プロジェクト最終的な成功度合い」+「プロセスでのリーダーシップや調整力」**をセットで見るイメージです。 - プロジェクト難易度をあらかじめレベル分けする
プロジェクトの規模、技術的複雑度、予算、納期、顧客の要望変動リスクなど、主要な要素をもとに難易度レベルを設定します。PMが高難易度のプロジェクトを成功裏に収めた場合は、その分だけ評価が高まるようなスコアリング方式を取り入れると、公平性が高まりやすくなります。 - 行動ベースの評価基準を明確にする
コミュニケーション、リーダーシップ、トラブル対応力などは抽象的ですが、**「こまめにリスクや課題を共有できているか」「週次レポートやミーティングを適切に実施しているか」「チームメンバーとの1on1を定期的に行っているか」**など、行動事例を具体化すれば評価がブレにくくなります。面談時に行動履歴やエビデンスを確認しながら評価する仕組みを作るのも有効です。
3. プロジェクトマネージャー向けの人事評価制度設計ポイント
ここからは、PM向けの評価制度を設計・運用する際に押さえておきたい具体的なポイントを「定量評価」「定性評価」「評価結果の活用方法」に分けて解説します。前章で紹介した課題を踏まえながら、自社のプロジェクト特性に合わせてカスタマイズしてみてください。
定量評価の主要ポイント3選
- 予算・コスト管理の精度
受注プロジェクトの場合、当初見積もりと実際のコスト・工数・利益率がどの程度乖離しているかは大きな評価材料になります。もちろん、顧客都合で追加要件が出た場合などは別途調整が必要ですが、PMが立てた計画と最終的な成果物にどの程度のギャップがあるかを数値化することで、一定の客観性を持った評価が可能です。 - 納期遵守率・品質指標
プロジェクトのスケジュール通りに進められたか、リリース時点のバグ数や顧客からのクレーム数など、完成度を示す指標も重要です。PMのマネジメント力が高いほど、想定外の遅延や大きな不具合を減らすことができます。ただし、仕様変更や予算カットなど、外部要因の影響を適宜考慮して評価する仕組みが必要です。 - プロジェクト難易度別の成功数・失敗数
前章でも触れましたが、プロジェクト難易度をレベル分けし、「レベル3(大規模・リスク高)プロジェクトを期限内&予算内で完了させた」という実績は高評価につなげる、といった仕組みが有効です。難易度が低い案件をいくら量産しても、PMの成長や能力を高く評価するのは難しく、逆に難易度が高いプロジェクトで結果を出したPMは組織に大きく貢献していると判断できます。
定性評価の主要ポイント3選
- リーダーシップ・チームビルディング
PMにはチームを引っ張り、適切にメンバーを配置・育成する役割が求められます。「プロジェクト開始時のキックオフや目標設定をスムーズに行った」「メンバーの強みを活かしたタスクアサインを実施した」「定期的な1on1やフィードバックで組織力を底上げした」などの行動事例を評価対象として明文化し、面談時に具体的なエピソードとともに確認します。 - コミュニケーション・ステークホルダー管理
顧客や社内外の関係者との折衝や調整において、PMがどれだけ円滑なコミュニケーションを実施できているかは、プロジェクト成功の大きな鍵です。**「顧客要望の変更があった際に迅速かつ明確にチームへ伝達し、スケジュール再調整を行った」「社内外のステークホルダーを巻き込むために定期ミーティングや報告を欠かさなかった」**といった事例を集め、プラス評価に繋げます。 - リスクマネジメントと問題解決力
PMはプロジェクト中に発生する様々なリスク(スケジュール遅延、技術的課題、人員不足など)を早期発見し、対策を講じる必要があります。トラブルに際して「どの段階で問題を察知し、どんな打ち手を取ったか」「その結果、被害を最小限に留めたか」など、PMとしての判断力や行動力を評価項目に組み込むことで、定性評価の精度を高めることができます。
評価結果の活用方法
昇給や賞与だけではなく、キャリアパス構築に活かす
PMのキャリアは、より大規模なプロジェクトを統括する上位PM、あるいは事業責任者や経営幹部的なポジションに進むなど、多彩な方向性が考えられます。また、技術をリードするテクニカルディレクター的な立場や、社内コンサルのような形にキャリア展開をするPMもいるでしょう。評価制度とキャリアパス設計を連動させることで、PM本人が「次に何を目指せばよいか」「どんなスキルアップが必要か」を明確に理解できます。
- 上位PMコース:大規模案件のマネジメント力、複数プロジェクトの同時管理スキル
- 経営層コース:事業推進力、利益責任、組織マネジメント
- スペシャリストコース:特定領域(AI、セキュリティなど)の深い知識を武器にリードする立場
評価結果を昇給やボーナスに反映するだけでなく、キャリア面談で長期的な目標設定に結びつけることで、PMのモチベーション向上と定着率改善が期待できます。
スキルマップや資格取得支援制度との連動
PMに必要なスキルは、プロジェクト管理(PMBOKなど)やアジャイル手法、コミュニケーション、財務知識など、多岐にわたります。会社としても、「どの知識やスキルを持ったPMがどれだけいるか」を把握し、研修や資格取得支援制度と紐づけることが大切です。たとえば、PMP資格取得やスクラムマスター認定などの成果を評価項目に反映すると、PM自らスキルを磨くインセンティブが働きやすくなるでしょう。
さらに、スキルマップを使えば、PMがどの領域に強みを持ち、どこが弱点かが可視化されます。これにより、社内で人材の最適配置を考える際や、後継者育成を検討する際にも役立ちます。たとえば、「大規模案件の経験値はあるが、経営視点が弱いPMには経理・財務の研修を受けてもらう」など、具体的なアクションを打ち出しやすくなるのです。

4. プロジェクトマネージャー向け 人事評価制度の活用事例
ここでは、実際にPM向けの評価制度を整備・運用して成果を上げている中小IT企業の事例を2つ紹介します。それぞれ企業の規模や事業特性、抱える課題が異なりますが、PMならではの評価項目や運用フローを工夫することで、組織全体のパフォーマンス向上につなげている点が参考になるでしょう。
事例1
導入背景
- 企業規模:社員数約30名(PMは2名、兼任PMも2名)
- 主な事業:Webシステムの受託開発と運用サポート
- 課題:プロジェクトリーダーが実質的にPMを兼務していたが、納期遅れや予算オーバーが頻繁に発生。原因として「PMが人手不足の中で現場作業もしながらマネジメントしている」「評価制度が整っていないので、PMが必要なスキルを満たしているか不明瞭」という問題が顕在化していた。
導入内容
- PM専任制度の導入と役割定義
社員の中からPM専任を2名選出し、「要件定義・進捗管理・予算管理・リスク対策」を主要任務とする役職を正式に設置。兼任PMには、やや小規模の案件を担当してもらい、難易度に応じて評価基準を変える仕組みを構築した。- 専任PM:大規模案件をリード、責任範囲も広く設定
- 兼任PM:中小規模案件、エンジニア業務との兼任を考慮した評価
- プロジェクト難易度×成果のスコアリング
プロジェクトを「難易度A(規模大・新技術多)」「難易度B(通常規模)」「難易度C(小規模)」の3つに分け、それぞれの成功指標(納期遵守率、予算オーバー率、顧客満足度など)をスコア化。さらに、スコアが高いほど評価が上がる仕組みを作成した。- 例:難易度A案件を想定内コスト+納期内で完遂→高スコア
- 定性評価:マネジメント行動を明文化
「顧客との定例ミーティングを月1回以上実施し、議事録をチームへ共有」「週次でリスクチェックを行い、課題管理表を更新」「メンバーの1on1を月1回実施」など、行動ベースの評価項目を設定。面談時に、実績をレポートやツールで確認しながら話し合うフローを定着させた。
成果
- 納期遅延や予算オーバーが顕著に減少し、プロジェクトごとの損益が安定した。
- 専任PMは、マネジメントに集中できる環境が整ったことで、リスク早期発見や顧客折衝が円滑に行えるようになった。
- 社員からは「何をすれば評価されるのかが明確」「兼任PMとしてのハードルや、専任PMを目指す道筋が分かりやすい」と好評を得た。
事例2
導入背景
- 企業規模:社員数約50名(PMは3名、兼任PMは5名程度)
- 主な事業:自社パッケージソフトの開発・販売、受託開発も一部実施
- 課題:ここ数年で案件規模が大きくなり、PMの負担が急増。「評価制度はある程度整備されていたが、PMに特化した項目が少なく、優秀なPMが正しく評価されているとは言い難い」状況が生まれていた。また、担当プロジェクトの難易度によって評価が不公平になる懸念が強かった。
導入内容
- PM専用の評価シート導入
全社員共通の評価制度に加え、PMだけが使用する評価シートを新設。**定量指標(納期遵守率、予算管理、顧客満足度)と定性指標(リーダーシップ、コミュニケーション、リスクマネジメント)**を組み合わせた形でスコア化する仕組みを取り入れた。評価シートにはプロジェクトの概要や難易度、メンバー構成などを記入する欄を設け、客観性を高めた。 - プロジェクト終了時の360度フィードバック
プロジェクト完了後、チームメンバーや関連部署、場合によっては顧客からのヒアリングを実施し、PMのマネジメント力やコミュニケーションの質を評価に反映。評価結果はまとめてPM本人にフィードバックされるが、誰がどのコメントをしたかは匿名化を徹底し、正直な声が集まりやすいよう配慮した。 - キャリアパス連動:PM→シニアPM→事業責任者
PM職を「PM(初級~中級)」「シニアPM(大規模案件を複数統括可能)」「事業責任者・幹部候補」へと段階的に定義。評価シートで高得点を継続的に獲得し、かつ幹部適性が認められた場合には経営会議への参加や新規事業検討プロジェクトへの配属など、キャリアアップの道筋が提示されるようになった。
成果
- メンバーや顧客のフィードバックを加味した多角的な評価により、PM自身も「自分のどこが強みで、どこを改善すべきか」が把握しやすくなった。
- 評価結果とキャリアパスが明確に結びついたことで、PMのやりがいが高まり、離職率が低下。リーダー職を目指す若手エンジニアも増え、組織の活性化に繋がった。
- 事業責任者クラスを新たに育成する仕組みができ、将来的な組織拡大に向けたリーダー層の人材確保が進んでいる。
5. まとめ
本コラムのポイント
- プロジェクトマネージャー(PM)は、進捗管理・リスク対策・顧客折衝・チームビルディングなど広範な役割を担い、企業の業績にも大きく影響する重要なポジション。
- 評価が難しい要因として、成果がプロジェクト全体の結果に溶け込みやすいことや、外部要因(顧客都合や技術リスクなど)の影響が強いこと、定性的なコミュニケーション・リーダーシップの評価が主観に寄りがちなことなどが挙げられる。
- この課題を解決するには、定量・定性の指標を組み合わせ、プロジェクト難易度の考慮、行動ベースの具体的評価基準の明確化が重要。また、結果をキャリアパスやスキルアップ施策と結びつけることで、PMのモチベーションや組織力向上につなげられる。
制度導入・運用における今後のステップ
- 評価制度の継続的な見直し(経営方針・事業規模の変化に合わせる)
企業が新たなプロダクトを立ち上げたり、受注案件の規模が大きくなったりすれば、PMに求められる要件も変わってきます。定期的に評価項目や難易度基準を見直し、現場の声を反映するプロセスを整えることが大切です。 - キャリアパス制度との連動性を強化して次世代人材の育成
PMの評価結果を昇給や賞与だけで終わらせず、**「シニアPM」「事業責任者」「スペシャリスト」**など複数のキャリアパスと繋げることで、PM本人の成長意欲を高め、組織としても中長期的なリーダー育成を促進できます。 - プロジェクトマネージャー職特有の事情を考慮した人事評価で業績向上を狙う
PMの質はプロジェクトの成否に直結し、納期・品質・顧客満足度やチームメンバーの成長にも大きく影響します。適切な評価制度を通じて優秀なPMを育成・定着させることは、企業の競争力を高める重要な戦略であると言えるでしょう。
本コラムでは、プロジェクトマネージャー(PM)に特化した人事評価制度のポイントと、実際の導入事例を解説しました。IT企業においては、プロジェクトの進め方や難易度は日々変化し、顧客要件や技術トレンドも多様化し続けています。そのような環境下でPMが果たす役割はますます重要になり、公正かつやる気を引き出す評価制度の整備が急務となるでしょう。
前回までのコラム(プログラマーやシステムエンジニアの評価など)を踏まえ、さらにPMという上流かつマネジメント色の強い職種をどう評価するかを考えることで、企業全体の人材育成や業績向上につなげることが可能です。評価制度は一度作ったら終わりではなく、現場の声やプロジェクト動向を反映しながら柔軟にアップデートしていくことが成功への近道です。今後も、ぜひ継続的な検討や改善を進めてみてください。
- IT業に特化【第1回】| 成功する評価基準と運用ポイント
- IT業に特化【第2回】| 人事評価制度を導入するメリット、デメリット
- IT業に特化【第3回】| プログラマーに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第4回】| システムエンジニアに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第5回】| プロジェクトマネージャーに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第6回】| Webデザイナーに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第7回】| ITコンサルタントに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- IT業に特化【第8回】| 効果的な人事評価制度の導入と成功の秘訣