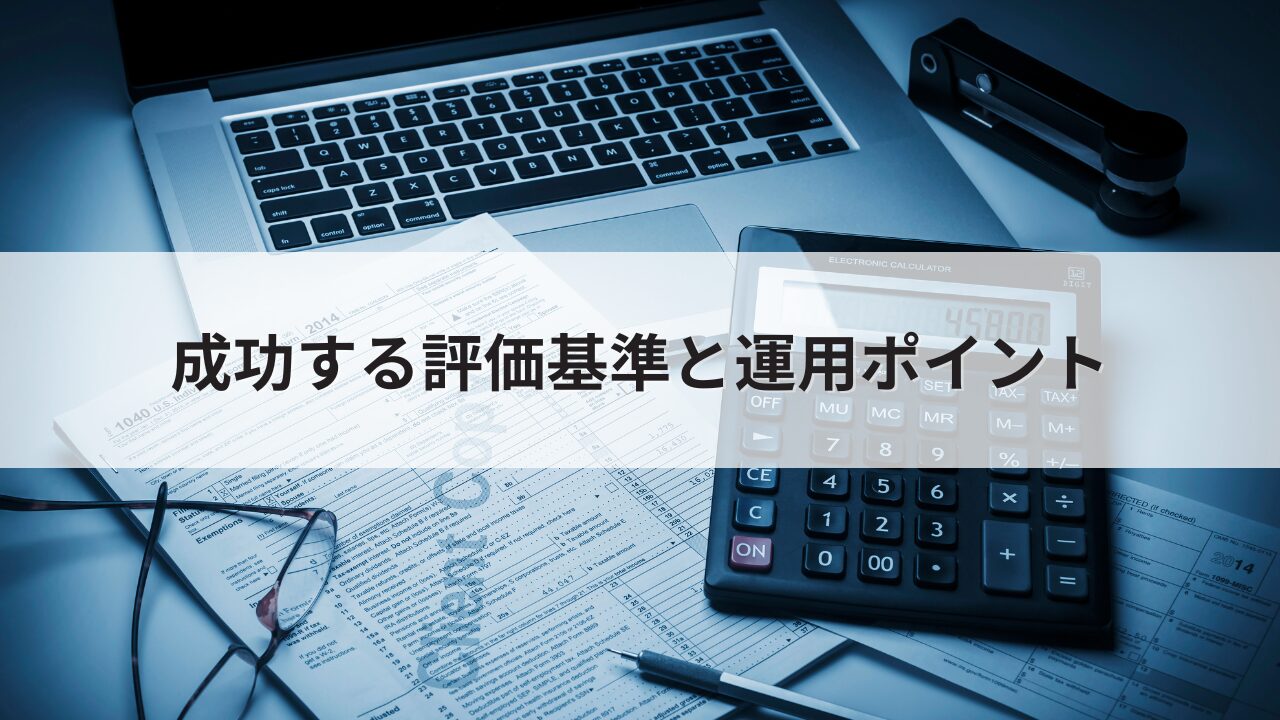1. はじめに
- 税理士事務所に特化【第1回】| 成功する評価基準と運用ポイント
- 税理士事務所に特化【第2回】| 人事評価制度を導入するメリット、デメリット
- 税理士事務所に特化【第3回】| 税理士に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 税理士事務所に特化【第4回】| 税理士補助に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 税理士事務所に特化【第5回】| 会計スタッフに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 税理士事務所に特化【第6回】| 営業職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 税理士事務所に特化【第7回】| 税務コンサルタントに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 税理士事務所に特化【第8回】| 効果的な人事評価制度の導入と成功の秘訣

1-1. 税理士事務所特有の人事課題
1-1-1. 採用面の課題
税理士事務所における採用は、一般企業とは異なる特有の難しさがあります。特に昨今では、会計・税務に対応できる人材が市場で不足しており、求職者側が複数の事務所を比較検討するケースも増えています。さらに、税理士資格の取得や科目合格を目指す方にとって、自身の学習環境やキャリアパスが明確であるかどうかは事務所選びの大きなポイントとなります。こうした背景から、単純な給与水準や労働条件だけでなく、評価制度やキャリア支援の仕組みが整備されているかどうかが採用の成否を大きく左右します。
また、税理士事務所の業務は繁忙期(3月や12月など)と閑散期の差が大きいため、忙しさのピーク時に人員が確保できないと業務量が集中してしまい、職場環境が悪化するリスクがあります。結果として、採用が追いつかずスタッフに大きな負荷がかかり、離職につながるという負のスパイラルが生じることも少なくありません。
1-1-2. 定着面の課題
採用に苦戦している税理士事務所では、ようやく採用した人材を長く定着させることが極めて重要です。しかし、定着を図るには、職場環境の快適さや人間関係の良好さに加えて、働きがいのある評価制度やキャリア形成の仕組みが欠かせません。特に若手スタッフや未経験者は、日々の業務を通じた成長実感を求める傾向が強く、適切に評価されていると感じられなければモチベーションが低下しやすくなります。
税理士事務所の大半は中小規模であるため、個々のスタッフが果たす役割が大きく、担当業務の幅や責任が広がりやすい一方で、「誰にどのような基準で評価され、昇給や昇進につながるのか」という仕組みが不透明になりがちです。評価制度があいまいなままだと、不満や不信感が蓄積して早期離職につながる可能性も高まります。
1-1-3. 育成面の課題
税理士事務所では、日常の業務に追われてスタッフの育成まで手が回らず、OJTが形骸化してしまうケースが多く見られます。特に繁忙期には業務優先になり、新人スタッフや若手へのフォローが不十分となる事務所も少なくありません。結果として、スタッフが学習機会を十分に得られず専門性が高まらない、または業務の効率を上げる手立てが見つからないといった問題につながります。
人材育成においては、研修やセミナーの受講機会を設けたり、資格取得をサポートする制度を整えたりといった施策が効果的です。ただし、これらの施策と人事評価制度が連動していないと、事務所としてどの能力をどのように評価し、スタッフにどのような行動を求めるのかがあいまいになり、育成効果が十分に発揮されません。評価制度と育成の仕組みが合致していなければ、事務所全体の業務レベルが底上げされるまでに時間がかかるか、もしくは成果を測定しにくくなる可能性があります。
1-2. 税理士事務所における人事評価制度の重要性
1-2-1. 採用面の重要性
人事評価制度を明確化・可視化することは、採用活動の大きな強みとなります。求職者から見れば、入所後にどのような基準で評価され、どのようにキャリアアップできるのかが明確な事務所は安心感が高いと言えます。単に給与や賞与の金額だけではなく、「努力した分だけ正当に評価される」「スキル習得や資格取得に前向きな姿勢が評価される」などの具体的な制度があることは、魅力的な職場の特徴です。
とりわけ、税理士や税理士を目指すスタッフにとって、評価制度があるかどうかは「自らのキャリアをどのように築いていけるか」を判断する重要な指標となります。また、評価制度の導入と運用により、事務所としてのブランディング効果も期待できます。近年はウェブサイトやSNSを通じた情報発信が盛んです。人事評価制度の有無や内容が外部に伝わることで、「この事務所はスタッフを大切にしている」「体系的にキャリアを築けそうだ」というプラスの印象を与え、採用競合の中で優位に立つことができるのです。
1-2-2. 定着面の重要性
採用した人材をいかに定着させるかは、税理士事務所の経営において最重要課題の一つです。評価制度が適切に機能すると、スタッフは「自分の業績や貢献度が正当に評価されている」と実感しやすくなり、やりがいやモチベーションを高める要因となります。また、評価結果をもとに報酬や昇給が決まる場合、スタッフは「次はどのスキルを身につければよいか」「どのような行動を取れば評価されるか」が明確になり、目標を持って意欲的に業務に取り組めます。
評価制度を通じて対話が促進されることも、定着率向上に寄与します。定期的な評価面談やフィードバックの場があることで、上司と部下のコミュニケーションが活性化し、トラブルやミスマッチを早期に発見・解決しやすくなります。また、個々のスタッフが自身のキャリアビジョンを上司と共有しやすくなるため、将来的な職務設計や異動に関する不安が軽減されるでしょう。
1-2-3. 育成面の重要性
評価制度を活用して人材育成を行うことで、事務所全体の底上げを図ることができます。日常業務で求められる専門知識や実務能力、またはコミュニケーション能力やリーダーシップなどの能力評価を行うことで、個々のスタッフが現在のレベルと課題を把握し、次に何を学習・習得すべきかが明確になります。これにより、スタッフは自分の成長軌道を描きやすくなり、モチベーションを高く保ちながら日々の業務に取り組めるようになります。
また、評価と同時に育成施策が行われると、学習の成果や業務改善の取り組みが評価に反映されるため、スタッフの行動に対してポジティブな循環が生まれます。たとえば、定期的な研修受講や資格取得に意欲的な姿勢が評価項目に含まれていれば、自然とスタッフは研修や学習機会を活用しようとします。その結果、事務所のサービス品質向上や業務効率化にもつながるわけです。

2. 評価基準を設定する際の重要ポイント
2-1. 税理士事務所特有の仕事特性
税理士事務所には、税理士や税理士補助、会計スタッフ、営業職、税務コンサルタントなど、複数の職種が存在します。それぞれに求められる能力や成果指標が異なり、キャリアパスも大きく異なるのが特徴です。そのため、評価基準を設定する際には「職種ごとの特性を正しく理解する」ことが不可欠です。以下では代表的な職種の特性を簡単に解説します。
2-1-1. 税理士の特性
税理士は専門家としての知識と経験を活かし、クライアントの税務申告や税務相談、経営アドバイスなどを行います。顧問先とのコミュニケーション能力や信頼関係構築力が重要となるのはもちろんですが、常に法改正に対応し、最新の知識をアップデートし続けることが求められます。また、スタッフや後進の育成に携わるケースも多いため、リーダーシップやマネジメントスキルが必要となる場合もあります。
2-1-2. 税理士補助の特性
税理士補助は、税理士の指示のもと決算書や申告書の作成、顧問先との連絡調整、各種手続きのサポートなどを行います。多くの場合、税理士資格の取得を目指す方が多いため、資格試験勉強と業務との両立が課題となります。評価基準としては、業務の正確性やクライアント対応の迅速性・丁寧さに加え、学習意欲や資格取得へのチャレンジ姿勢も重要視される場合が少なくありません。
2-1-3. 会計スタッフの特性
会計スタッフは、仕訳入力・帳簿作成・試算表作成など、主に記帳代行や月次決算の業務を担います。業務の正確性とスピードが重要であり、ミスを防ぐための確認作業やコミュニケーションが欠かせません。また、税理士補助と業務範囲が重なることもありますが、資格を保有していない場合でも、業務の中で経験を積みながらキャリアアップしていくケースも多い職種です。
2-1-4. 営業職の特性
税理士事務所によっては、積極的に新規顧問先を開拓する営業担当を置く事務所もあります。営業職には、税理士やスタッフが提供できるサービスの提案能力や、顧客ニーズを的確に汲み取るヒアリングスキルが求められます。さらに、税理士の専門知識をある程度把握し、クライアントへ分かりやすく説明する力も重要となります。成果指標は「新規顧客獲得数」「契約更新率」など、比較的定量的に測りやすい部分がある一方で、長期的には「既存顧客との関係強化」など定性的な要素も考慮する必要があります。
2-1-5. 税務コンサルタントの特性
税務コンサルタントは、法人税や所得税だけでなく、相続税や国際税務など、より高度で専門的な分野に対応する役割を担う場合が多いです。高い専門知識と分析力、そしてクライアントごとにカスタマイズした提案力が必要になります。評価項目としては、コンサルティングの成果(節税額やコスト削減効果、クライアント満足度)だけでなく、案件をスムーズに進行させるプロジェクトマネジメント能力なども加味されることが多いです。
2-2. 税理士事務所特有の評価基準
2-2-1. 定量的な評価基準
定量的な評価基準とは、売上や利益、顧客数、案件数、ミス発生率など、数値化しやすい指標を用いた評価を指します。営業職の場合は「新規契約の件数・金額」、税理士や税理士補助の場合は「担当顧問先の満足度」「決算・申告スケジュールの遵守率」「書類作成におけるミスの有無・回数」などが挙げられます。定量的評価のメリットは、結果が明確に示されるためスタッフも納得しやすく、評価の客観性が高まりやすいことです。一方で、税理士事務所では繁忙期・閑散期の差や、担当顧問先の業種や規模によって数値のバラつきが生じやすいことも踏まえ、単純比較が難しい場合があります。そのため、数値の目標設定は個人の担当領域や経験年数に応じて調整し、公平感を担保する必要があります。
2-2-2. 定性的な評価基準
税理士事務所における業務には、クライアントとの信頼関係構築や、スタッフ間の協力体制の構築、問題解決力や提案力など、数値では測りきれない要素が多く含まれます。そこで重要なのが、定性的な評価基準です。例としては、以下のような項目が考えられます。
- コミュニケーション力:クライアントや同僚、上司との円滑なやり取り、情報共有の適切さなど
- リーダーシップ・マネジメント力:後輩指導の方法、チームの目標達成への貢献度合いなど
- 問題解決力・提案力:クライアントの課題を把握し、改善策や新しいサービスを提案できるか
- 主体性・成長意欲:資格取得や研修受講など、自主的にスキルアップを図る姿勢
定性的な評価を行う際には、評価基準の明確化が非常に重要です。「人柄が良い」「頑張っている」という曖昧な表現だけでは、評価される側もどのように行動すればよいか分かりません。評価表の項目を細分化し、「成果はどの程度のレベルに達しているか」「どのような行動が評価されるのか」を具体的に示す必要があります。

3. 運用を成功させるためのポイント
3-1. 評価者の育成(評価者研修・面談スキル)
評価制度を導入するうえで見落とされがちなのが、「評価者の育成」です。どんなに優れた評価システムを構築しても、実際に評価を行う税理士や上司が適切な判断を下せなければ、公平性や透明性は担保されません。評価基準の理解を深め、面談の進め方やフィードバックの手法を習得するための研修を行うことが効果的です。
特に税理士事務所では、プレイヤーとしての業務が忙しく、人事評価に時間を割きづらい傾向があります。しかし、評価者が「評価基準やプロセスを正しく理解しているか」「スタッフの成長を引き出す面談スキルを持っているか」は、制度の運用成否を大きく左右します。そのため、事務所内での研修や外部講師の招致などを検討し、評価者の意識とスキルを高めていくことが欠かせません。
3-2. フィードバック面談の重要性とポイント
評価制度は「点数付け」で終わらせるのではなく、「次の行動を促す」ために活用されることが理想です。そのためには、評価結果をスタッフに還元するフィードバック面談が不可欠です。フィードバック面談では、以下のようなポイントが重要となります。
- 具体的な根拠を示す
「前回の評価からどのように改善されたか」「どのような場面で期待以上の成果が見られたか」など、定量・定性的な観点の両方から具体的な事例を示して評価することで、スタッフの納得感が高まります。 - 今後の目標や成長課題を一緒に考える
単に評価結果を伝えるだけでなく、「次に何をすべきか」を一緒に考える場とすることで、スタッフのモチベーション向上と行動変容を促します。 - 傾聴と共感
スタッフの立場や悩みに寄り添うことで信頼関係を強化し、評価制度そのものへの不信感や抵抗感を軽減します。
定期的なフィードバック面談を通じて、評価が単なる「区分け」ではなく「コミュニケーションのきっかけ」や「成長のステップ」として機能するよう、事務所として仕組み化を図ることが大切です。
3-3. 評価結果の活用方法
評価結果は、昇給や昇進といった処遇だけでなく、事務所の業務改善や組織強化に幅広く活用できます。例えば、スタッフごとの強みや課題を分析して適材適所の配置を行うことで、チーム全体のパフォーマンスを引き上げることが可能です。また、スキル不足や知識不足が評価から明らかになった場合は、それを基に研修カリキュラムを作成したり、外部のセミナーを案内したりするなど、ターゲットを絞った育成施策を立案できます。
さらに、評価結果をスタッフと共有することで「自分は何が得意なのか」「どこを伸ばせばよいのか」が明確になり、自己理解とモチベーションアップにつながります。ただし、評価結果の公表範囲はプライバシー保護や組織風土を考慮し、適切に設定する必要があります。評価制度の透明性を高める一方で、個々人の評価内容をどこまで開示するかは事務所の文化やスタッフの性格傾向に合わせて検討することが大切です。
3-4. 育成計画・キャリアパス設計への活用
評価制度の導入は、スタッフのキャリアパスを明確化する絶好の機会でもあります。評価基準をもとに、「一定のレベルに達すればどのような役割を担えるのか」「どの資格やスキルを獲得すれば新たな業務範囲を任されるのか」を体系化することで、スタッフは将来像をイメージしやすくなります。特に税理士や科目合格者にとっては、どの時点でどのような責任や裁量を与えられるのかが明確になれば、事務所内で長期的にキャリアを積みたいという意欲が高まるでしょう。
また、キャリアパス設計の中で、評価制度と連動した研修プログラムやOJT体制を整備することで、短期的な成果だけでなく中長期的な人材育成と組織力強化にもつなげやすくなります。たとえば、新人スタッフには基礎的な知識習得と簡単な業務から始め、中堅スタッフにはチームリーダーとしてのマネジメント力を習得させるなど、段階的・計画的にスキルアップを図る仕組みを構築するのです。
3-5. 社員モチベーション向上施策との連動
評価制度は決して単独の仕組みではなく、給与制度や表彰制度、各種研修や福利厚生などと連動させることで相乗効果を生み出します。例えば、評価によって「事務所の目標達成に大きく貢献したスタッフ」を表彰する仕組みを設ければ、他のスタッフにとっても明確な成功事例が提示され、モチベーションの向上につながります。また、一定の評価結果を得たスタッフに対して特別休暇や海外研修への参加権などインセンティブを付与する事例もあります。
このように、事務所の経営方針や組織文化に合った施策をうまく組み合わせることで、人事評価制度の効果をより強固にし、スタッフが「評価されること」を自発的な成長の原動力に変えられるようになるのです。
4. 実践のヒント・具体例
ここでは、税理士事務所が評価制度を導入・運用する際に役立つ具体例やヒントをいくつかご紹介します。
- 目標管理シートの導入
業務目標や学習目標、行動目標などをシートに落とし込み、定期的に上司とすり合わせる仕組みを作ります。繁忙期・閑散期のタイミングを考慮して、四半期ごとや半期ごとに面談を実施するのも効果的です。 - 専門分野ごとのスキルマップ作成
税理士事務所は法人税、相続税、消費税、国際税務など、扱う専門分野が多岐にわたります。スタッフ各々がどの領域に強みを持ち、どの領域でスキルが不足しているかを視覚化することで、客観的かつ公平な評価と育成が行いやすくなります。 - ロールプレイによる評価者訓練
評価者研修の一環として、実際の評価面談を想定したロールプレイを行うのは有効です。想定される質問や不満に対する応答例を蓄積しておくことで、評価者の面談スキルが向上し、スタッフへのフィードバックの質も上がります。 - 自己評価の仕組み
スタッフ自身にも自己評価を行ってもらい、その結果を評価者とすり合わせる場を設けると、評価に対する納得感が高まりやすくなります。自己評価は客観視が難しい部分もありますが、自分自身がどのように感じ、どの程度の成果を出したと捉えているかを把握することは、評価者にとっても重要な判断材料となるでしょう。 - 短期と長期の目標を設定
「直近の繁忙期を乗り切る」という短期目標と、「3年後に税理士資格を取得する」「5年後に特定分野のプロとして活躍する」といった長期目標を組み合わせることで、日々の業務に追われながらも将来のビジョンを見失わずに評価を活用できます。 - 社内勉強会や知識共有会の開催
評価で明らかになったスタッフの得意分野や成功事例をシェアすることで、組織全体の知識レベルと士気が高まります。評価制度と直接的には関連しないように見えますが、このような取り組みが定性的評価にもポジティブに作用しやすくなります。

5. まとめ
5-1. ポイントの再確認
本コラムでは、税理士事務所の人事評価制度を成功に導くうえで押さえておきたいポイントについて、以下の流れで解説してきました。
- はじめに:税理士事務所特有の人事課題と評価制度の重要性
- 評価基準の設定:定量・定性の両軸から職種特性に合った指標を検討
- 運用を成功させるためのポイント:評価者育成、フィードバック面談、評価結果の活用など
- 実践のヒント・具体例:目標管理シートの導入やスキルマップ作成、ロールプレイ研修など
税理士事務所の経営者・人事担当者の方々にとって、評価制度は人材の採用・定着・育成を円滑に進めるための重要な基盤です。次回以降のコラムでも、評価制度のメリットやデメリット、具体的な導入事例などをより深く掘り下げていきます。
5-2. 税理士事務所に合った評価項目の設定
税理士事務所には、税理士・税理士補助・会計スタッフ・営業職・税務コンサルタントなど、多岐にわたる職種が存在します。職種によって求められる能力・成果指標が異なるため、あらかじめ 職種別の特性と事務所の方針 を踏まえ、定量・定性の双方から評価項目を設定することが重要です。また、スタッフの経験年数や担当顧問先の業種・規模によっても個別に目標を調整するなど、公平感と納得感を高める工夫が欠かせません。
5-3. 評価者育成とフィードバック面談の重要性
最後に、評価制度を形骸化させないためには、評価者のスキルと制度運用のプロセス整備 が不可欠です。評価者研修による基準の統一や面談ノウハウの習得、定期的なフィードバック面談の実施などにより、スタッフとのコミュニケーションを活発にすることで、評価を「成長につなげるための仕組み」として活用できるようになります。そうした取り組みを続けることで、採用難や離職率の高さなど、税理士事務所が抱える人事課題を根本的に解決できる可能性が高まります。
ここまでご紹介した内容を踏まえつつ、次回のコラムでは「税理士事務所の人事評価制度を導入するメリットとデメリット」を中心に解説します。評価制度を検討しているものの、導入に際するデメリットや注意点、導入後のイメージがつかみにくいという声も多く耳にします。そこで、第2回では 導入メリット・デメリットの具体例 に加え、導入に成功した実例も取り上げながら、皆さまの事務所で実践しやすいヒントをお届けしていきたいと思います。
税理士事務所の人事評価制度は、一度設計すれば終わりというわけではなく、事務所の成長やスタッフの変化に合わせて 定期的に見直しながらブラッシュアップ していくことが大切です。本コラムが、皆さまの評価制度構築に少しでも役立ち、組織とスタッフ双方の成長につながることを願っております。次回もぜひお楽しみにしてください。
- 税理士事務所に特化【第1回】| 成功する評価基準と運用ポイント
- 税理士事務所に特化【第2回】| 人事評価制度を導入するメリット、デメリット
- 税理士事務所に特化【第3回】| 税理士に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 税理士事務所に特化【第4回】| 税理士補助に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 税理士事務所に特化【第5回】| 会計スタッフに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 税理士事務所に特化【第6回】| 営業職に活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 税理士事務所に特化【第7回】| 税務コンサルタントに活用できる人事評価制度のポイントと事例紹介
- 税理士事務所に特化【第8回】| 効果的な人事評価制度の導入と成功の秘訣